【高校化学】酸化と還元をまるごと理解!酸素・水素・電子・酸化数の変化を表で覚えよう
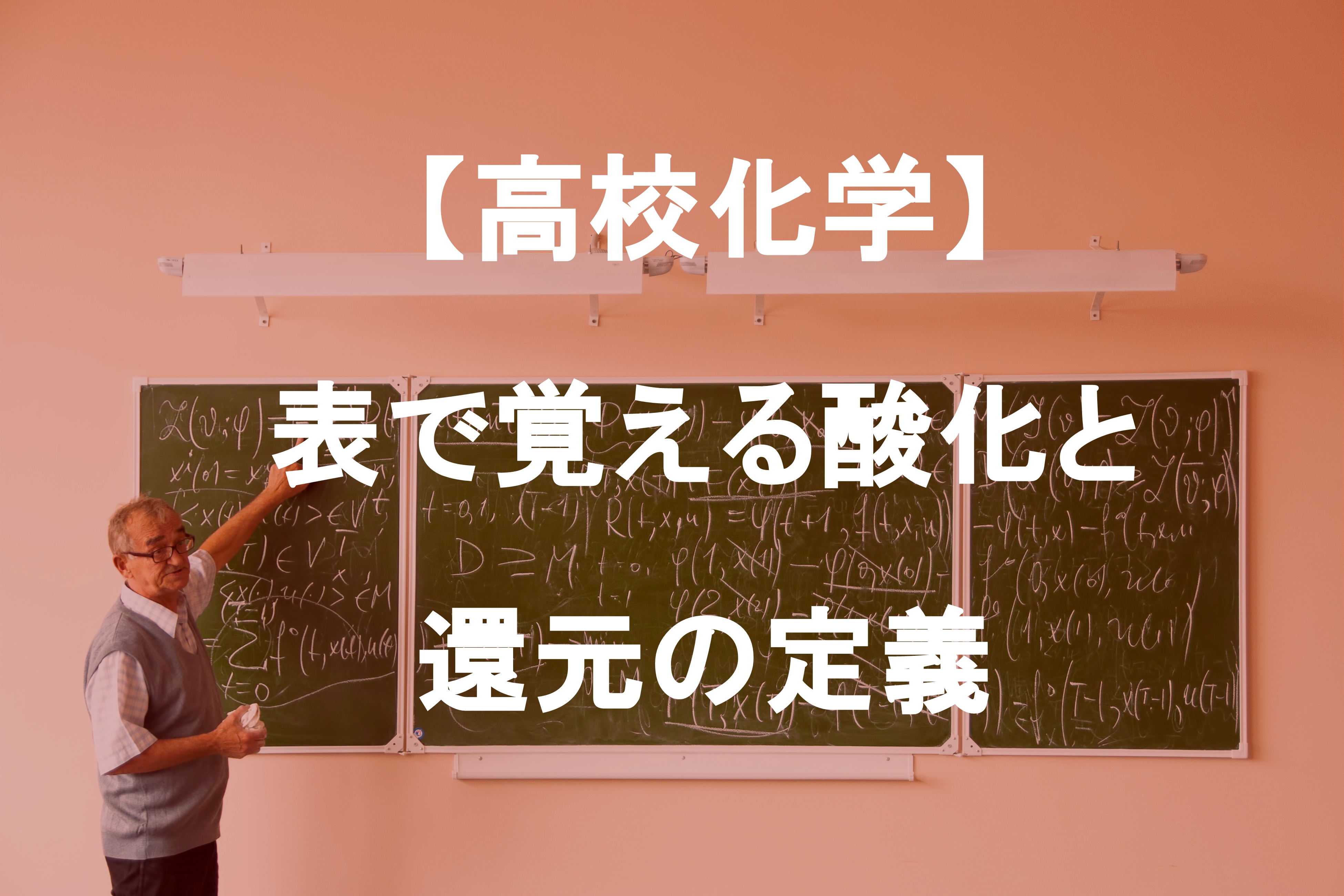
こんにちは!櫻學舎講師の菊池涼です。
「酸化と還元」は、高校化学の中でもよく出てくる超重要テーマ。
でも実際に勉強してみると──
- 「定義がいくつもあって、どれが正しいのか分からない」
- 「酸素? 水素? 電子? 酸化数? 覚えることが多すぎ!」
- 「結局、何を基準に酸化・還元を判断すればいいの?」
…そんなふうに感じたことはありませんか?
この記事では、酸化と還元の基本から、
酸素・水素・電子・酸化数 という4つの視点に分けて、それぞれの定義と特徴をわかりやすく解説します。
さらに、最後には「変化が一目でわかる表」で総まとめ。
「酸化と還元って、こういうことだったのか!」とスッキリ理解できるようになります。
模試や定期テストでも頻出のこの単元を、この記事で一気にマスターしましょう!にしていきましょう!
酸化と還元の基本定義
まずは「酸化」と「還元」という言葉の一番基本的な定義を確認しましょう。
この定義は主に“酸素の関わり方”に注目したものです。
- 酸化:物質が酸素と化合する反応
- 還元:物質が酸素を失う反応
たとえば、鉄が空気中で酸素と反応してサビになる反応(Fe → Fe₂O₃)は「酸化」ですし、
一方で酸化銅(CuO)から酸素を取り除いて銅(Cu)に戻す反応は「還元」にあたります。
この「酸素が関わるかどうか」で判断する定義は、化学の歴史の中でも最初に使われていたものです。
しかし実際の化学反応では、酸素だけでなく水素や電子、酸化数の変化などにも注目する必要があります。
なぜなら、例えば電池や電気分解のような分野では、酸素が出てこない反応でも酸化・還元が起こるからです。
そのため、現代の高校化学では以下のような4つの観点で「酸化と還元」を定義するのが一般的になっています。
酸化と還元の4つの見方
- 酸素の移動で考える
- 水素の移動で考える
- 電子の移動で考える
- 酸化数の変化で考える
このあとのセクションでは、それぞれの視点から酸化と還元をわかりやすく解説し、
最後に全体を一つの表で整理して覚えられるようにしていきます。
酸素と水素の移動で見る酸化・還元

酸化と還元の定義にはいくつかの視点がありますが、まずは「酸素」と「水素」の移動に注目してみましょう。
これらは視覚的にもイメージしやすく、化学反応の中で何が起こっているかを直感的に理解する手助けになります。
酸素の移動による定義
酸化と還元を酸素の動きで説明すると、以下のようになります。
- 酸化:酸素を受け取る(得る)反応
- 還元:酸素を手放す(失う)反応
例:銅と酸素の反応
$$2Cu+O2→2CuO$$
この反応では、銅(Cu)が酸素(O)と結びついて酸化銅(CuO)になるため、「銅が酸化された」と言えます。
水素の移動による定義
一方、水素に注目して酸化・還元を説明すると、定義は酸素とは逆になります。
- 酸化:水素を失う反応
- 還元:水素を受け取る(得る)反応
例:酸化銅と水素の反応
$$CuO+H2→Cu+H2O$$
この反応では、酸化銅が水素によって銅に戻る(酸素を失う)ため、「酸化銅が還元された」と言えます。
同時に、水素が水(H₂O)になることで酸素と結合=酸化されたこともわかります。
ポイントまとめ
- 酸化:酸素を得る/水素を失う
- 還元:酸素を失う/水素を得る
このように、酸素と水素は酸化・還元において“逆の立場”として作用します。
この関係をセットで覚えておくと、テストでの判断が速くなります。
電子の移動で見る酸化・還元
化学反応の中には、酸素や水素が関係しないものもあります。
特に電池や電気分解などの分野では、電子(e⁻)のやり取りをもとに酸化・還元を判断することが重要になります。
この考え方は、高校化学における電気化学の基礎でもあり、確実に押さえておきたいポイントです。
電子の移動による定義
- 酸化:電子を失う反応
- 還元:電子を受け取る(得る)反応
この定義を理解することで、電子が関与するすべての化学反応に対応できるようになります。
具体例で理解しよう
例1:銅イオンが電子を受け取って金属銅に戻る
$$Cu2++2e−→Cu$$
この反応では、銅イオン(Cu²⁺)が電子を受け取って銅(Cu)になるため、還元反応です。
例2:塩化物イオンが電子を放出して塩素分子になる
$$2Cl−→Cl2+2e−$$
こちらは、塩化物イオン(Cl⁻)が電子を放出して塩素(Cl₂)になる反応なので、酸化反応になります。
暗記のコツ:「電子=水素」のイメージで
水素は「還元」に関わる代表的な元素です。
同じように、電子も“与えると酸化、受け取ると還元”というルールに従っています。
そのため、電子は“水素みたいなもの”として覚えておくと、
「水素を得る=還元」「電子を得る=還元」とセットでイメージしやすくなります。
ポイントまとめ
- 酸化:電子を失う(=e⁻ を放出)
- 還元:電子を得る(=e⁻ を受け取る)
- 「電子が動く=化学反応が起こる」という視点は、電池・電気分解などの理解にもつながる
酸化数の変化で見る酸化・還元
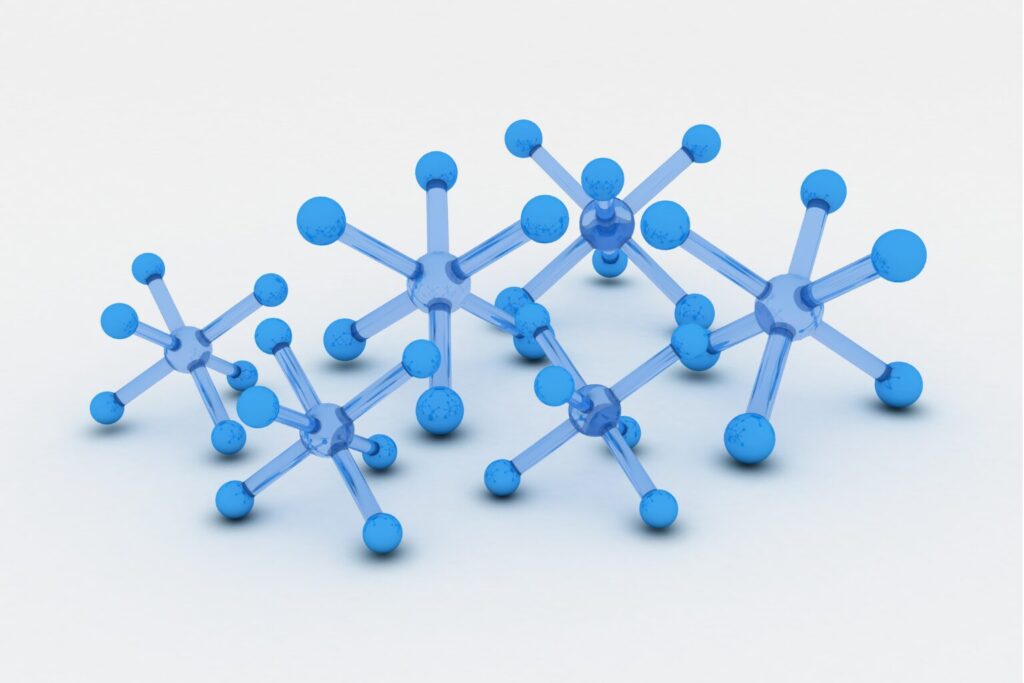
化学反応の中で「どの物質が酸化され、どの物質が還元されたか」を判断するために最も確実なのが、酸化数の変化に注目する方法です。
特に化学反応式の問題や酸化還元反応式の作成では、酸化数の変化に基づく判断が必須になります。
酸化数とは?
酸化数とは、原子が電子をどれだけ失ったか・得たかを数値で表したものです。
イオンや化合物の中での原子の“電子の持ち方”を数値化することで、反応前後の変化を見比べられるようになります。
酸化数の基本ルール
以下は高校化学で覚えておくべき酸化数の基本ルールです:
- 単体(例:O₂, H₂, Fe)の酸化数は 0
- イオン(例:Na⁺, Cl⁻) の酸化数は、そのイオンの電荷と同じ
- 水素(H)の酸化数は通常 +1
- 酸素(O)の酸化数は通常 –2
- 中性分子では、構成原子の酸化数の合計は 0
- 多原子イオンでは、構成原子の酸化数の合計は イオンの電荷と一致
- アルカリ金属(Na, Kなど)は常に +1、アルカリ土類金属(Mg, Caなど)は常に +2
これらのルールをもとに、反応前後で酸化数が増えたか、減ったかを見ていきます。
酸化と還元の酸化数変化
- 酸化:酸化数が増加する(=電子を失う)
- 還元:酸化数が減少する(=電子を受け取る)
例1:酸化(電子を失う)
$$Fe2+→Fe3++e−$$
→ 酸化数が +2 から +3 に増えている → 酸化
例2:還元(電子を得る)
$$MnO4−+5e−→Mn2+$$
→ 酸化数が +7 から +2 に下がっている → 還元
なぜ酸化数を使うのか?
- 酸素や電子が出てこない反応でも「酸化・還元」を判断できる
- 酸化数の変化量を使って電子のやりとりのバランスをとることで、半反応式やイオン反応式を正確に書ける
- 「見えない電子の流れ」が数値で表現できるようになる
ポイントまとめ
- 酸化:酸化数が増える(+方向)=電子を失う
- 還元:酸化数が減る(−方向)=電子を受け取る
- 酸化数は「見えない電子の移動」を見える形にするツール
酸化と還元の変化まるわかり表
ここまで、酸化と還元を「酸素」「水素」「電子」「酸化数」という4つの視点から見てきました。
それぞれの定義を別々に覚えるのは大変に思えるかもしれませんが、実はすべての視点で共通する“変化の向き”があります。
以下の表にまとめることで、酸化と還元の違いが一目で整理できます。
酸化と還元の比較表
| 観点 | 酸化 | 還元 |
|---|---|---|
| 水素 | 失う(−) | 得る(+) |
| 酸素 | 得る(+) | 失う(−) |
| 電子 | 失う(−) | 得る(+) |
| 酸化数 | 増える(+) | 減る(−) |
覚え方のコツ:「酸化=3つのプラス」
酸化の特徴を簡単に覚えるために、「酸化=酸素・酸化数・プラス」とまとめるのがおすすめです。
- 酸素を得る → プラス
- 酸化数が増える → プラス
- 電子を失う → マイナスだけど、酸化反応の原因として“前向きな変化”と覚えてもOK
- 水素を失う → 反対に還元で“得る”ので、ペアで記憶
このように「酸化=プラスの変化」「還元=マイナスの変化」として全体を捉えると、頭の中で方向性がそろって覚えやすくなります。
暗記フレーズ例:「酸化の3酸+(さんさんプラス)」
- 酸素 → +
- 酸化数 → +
- “酸”化だから → “酸”素と“酸”化数に注目
- +が3つで「酸化の3酸+」とゴロで覚えておくと定着しやすい!
この表と覚え方をノートに書き写し、繰り返し確認することで、どんな形式の問題にも自信を持って取り組めるようになります。
まとめ|酸化と還元を完全攻略!
酸化と還元は、高校化学のあらゆる単元の“土台”ともいえる重要な概念です。
今回は、4つの観点(酸素・水素・電子・酸化数)からそれぞれの定義を整理し、最後に一覧表で全体像を把握できるようにしました。
それぞれの視点を振り返ると:
- 酸素の移動:酸化=酸素を得る、還元=酸素を失う
- 水素の移動:酸化=水素を失う、還元=水素を得る
- 電子の移動:酸化=電子を失う、還元=電子を得る
- 酸化数の変化:酸化=酸化数が増える、還元=酸化数が減る
そして、これらをまとめた「まるわかり表」と「暗記フレーズ(酸化の3酸+)」を活用すれば、混乱しがちな酸化・還元の判定もスムーズにできるようになります。
最後にアドバイス
酸化と還元は、一度理解すれば電池・電気分解・無機化学・有機化学と、あらゆる単元に応用できます。
この記事で学んだことをもとに、
- 教科書や問題集の反応式を「誰が酸化?誰が還元?」と意識して読んでみる
- ノートに表を書き写して、自分なりの言葉で整理してみる
- 実際の入試問題や模試で、判断に迷ったときに“酸化数”を使って冷静に分析する
といったステップで、知識を実践に結びつけていきましょう。
繰り返しになりますが、酸化と還元を理解することは、化学全体を理解することに直結します。
ここでしっかり身につけて、得意分野として活かしていきましょう!








