【中学5教科】記述問題がスラスラ解ける!解答のコツと勉強法を徹底解説!
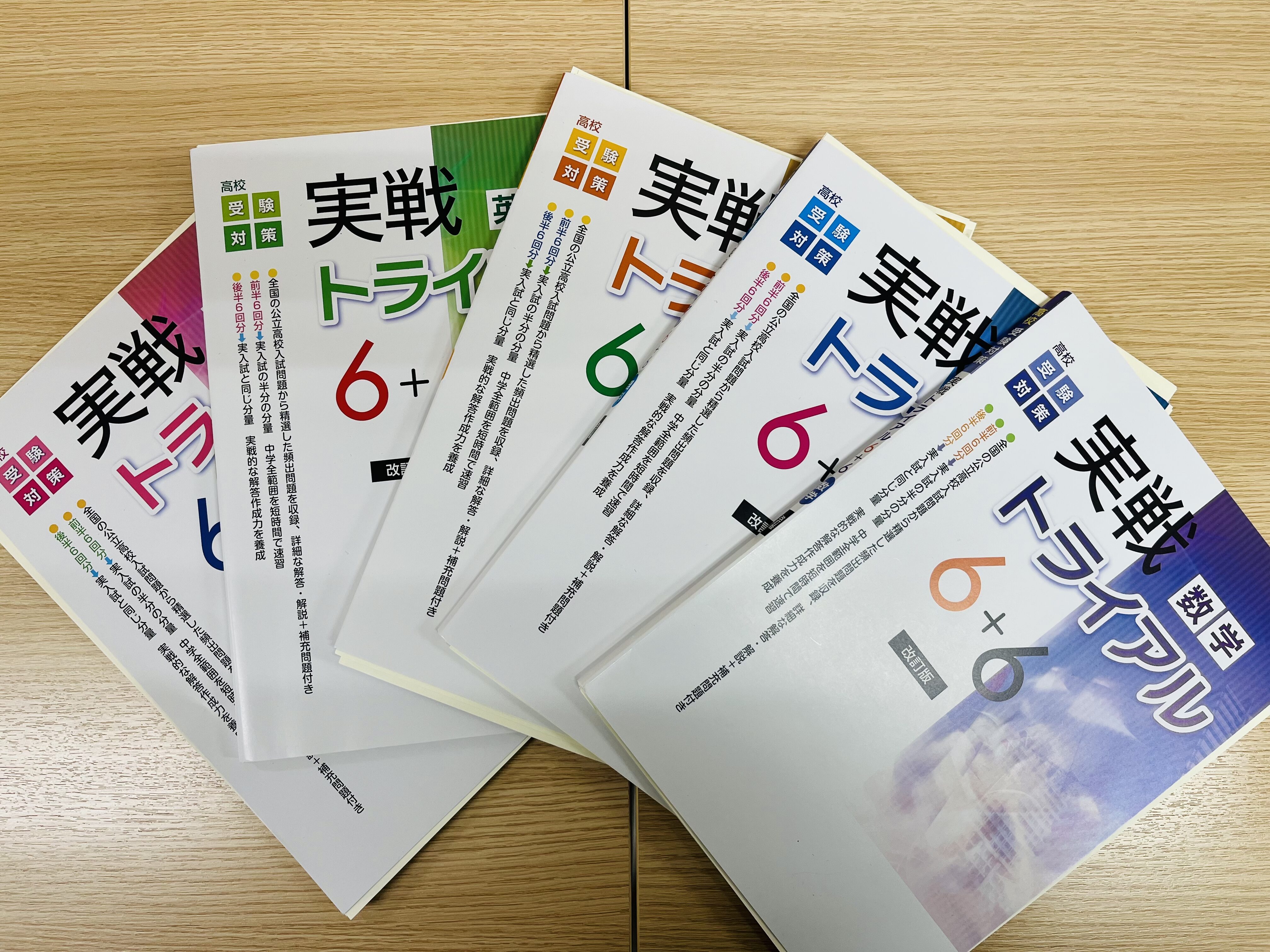
「記述問題が苦手…」「答えは分かるのに、文章にするとまとまらない…」 こうした悩みを抱えている中学生はとても多くいます。
定期テストや模試、そして入試でも頻出の“記述問題”。
配点も高く、ここで失点してしまうと全体の点数に大きく響いてしまいます。
でも、逆に言えば、
「書き方のルール」さえ分かれば、だれでも記述問題は得点源になります!
この記事では、記述問題が苦手な人でも自信を持って解けるようになるために、5教科別にそのコツと対策をわかりやすく紹介します。
記述問題が苦手な人に共通する悩み
記述問題を苦手とする中学生の多くは、次のような悩みを持っています。
- 「何をどう書けばいいか分からない」
- 「頭の中には答えがあるけど、文章にするのが難しい」
- 「書き始めても、途中で詰まってしまう」
このようなつまずきは、「設問の意図」と「記述の型」を意識するだけで、大きく改善することができます。
記述問題を解く3つの基本ルール
設問の意図を読み取る
「なぜ」「どのように」「どうなる」といった問いには、それぞれ求められている答え方があります。
問題文を読みながら、「これは理由を聞いているのか? それとも結果を聞いているのか?」と考える習慣をつけましょう。
書き方の「型」を覚える
記述問題には定番の構文パターンがあります。
- 原因:「〇〇の理由は、△△だからである。」
- 結果:「その結果、〇〇となった。」
- 仕組み:「〇〇は△△の働きにより□□になる。」
このような「型」に当てはめれば、考えがスムーズに文章化できます。
書く前にメモで整理する
いきなり解答用紙に書き始めるのではなく、まずは頭の中を整理することが大切です。
箇条書きで「答えに入れたい要素」をまとめてから、それらを文章にしていくと、迷わず書けるようになります。
国語の記述問題:筆者の考えを読み取る
国語では「筆者の考え」や「登場人物の気持ち」を説明する記述がよく出題されます。答えは本文の中に必ずあるので、接続語に注目しましょう。
- 「だから」「しかし」の後に、筆者の主張が出ることが多い
- 「例えば」の前後には考えと具体例の関係がある
文章にする際は、
- 「〇〇と考えている。それは△△だからである。」
- 「〇〇という状況で、△△と感じた。」
というような型を使うとまとまりやすくなります。
数学の記述問題:証明や説明
数学では、図形の証明や式の導出など、論理の積み重ねが問われます。
まずは、「何を証明するか」を明確にします。
そのうえで、
- 仮定:「仮定より、〇〇である。」
- 適用:「△△の性質を使うと□□がわかる。」
- 結論:「したがって、〇〇が証明された。」
と、順序立てて記述していきましょう。
社会の記述問題:歴史や制度の因果関係
社会科の記述では、原因・経過・結果の3ステップで説明すると分かりやすくなります。
例えば「地租改正」について書くなら、
- 原因:税収の安定化を図るため
- 経過:土地所有者が地価に応じて現金納税
- 結果:農民の負担が増し、一揆が起きた
というように、順を追って整理すると、読み手に伝わりやすい文章が作れます。
理科の記述問題:現象のしくみや理由
理科では「なぜそうなるのか?」という問いが多く出されます。
ポイントは、専門用語を正確に使うことです。
例えば、浮力についての問題であれば、「浮力は、物体が押しのけた水の体積に比例するため、体積が増えると浮力も大きくなる。」
のように、原理をきちんと説明できることが求められます。
よくある失敗とその対策
記述問題では、次のようなつまずきがよく見られます。
- 書き出しで止まってしまう
→ メモを取って整理してから書く - 文章が長くなりすぎて意味不明
→ 一文一意を意識する - 答えがぼんやりしている
→ 原因・しくみ・結果のどこを聞かれているかを明確に - 語句があいまい
→ 教科書や資料集で用語の意味を確認する
まとめ:記述問題は「練習すれば必ず伸びる」力

記述問題は「センス」ではなく、「慣れと準備」です。
型を身につけ、練習を重ねれば、誰でも得点できるようになります。
そして、記述力は入試だけでなく、将来社会に出てからも「伝える力」として役立ちます。
最初からうまく書けなくても大丈夫。
あきらめずに、1問ずつ丁寧に練習していきましょう。あなたの言葉で、自分の考えを伝える力を育てていきましょう。








