【中学理科】記述問題が苦手でも大丈夫!スラスラ書ける解答のコツと勉強法
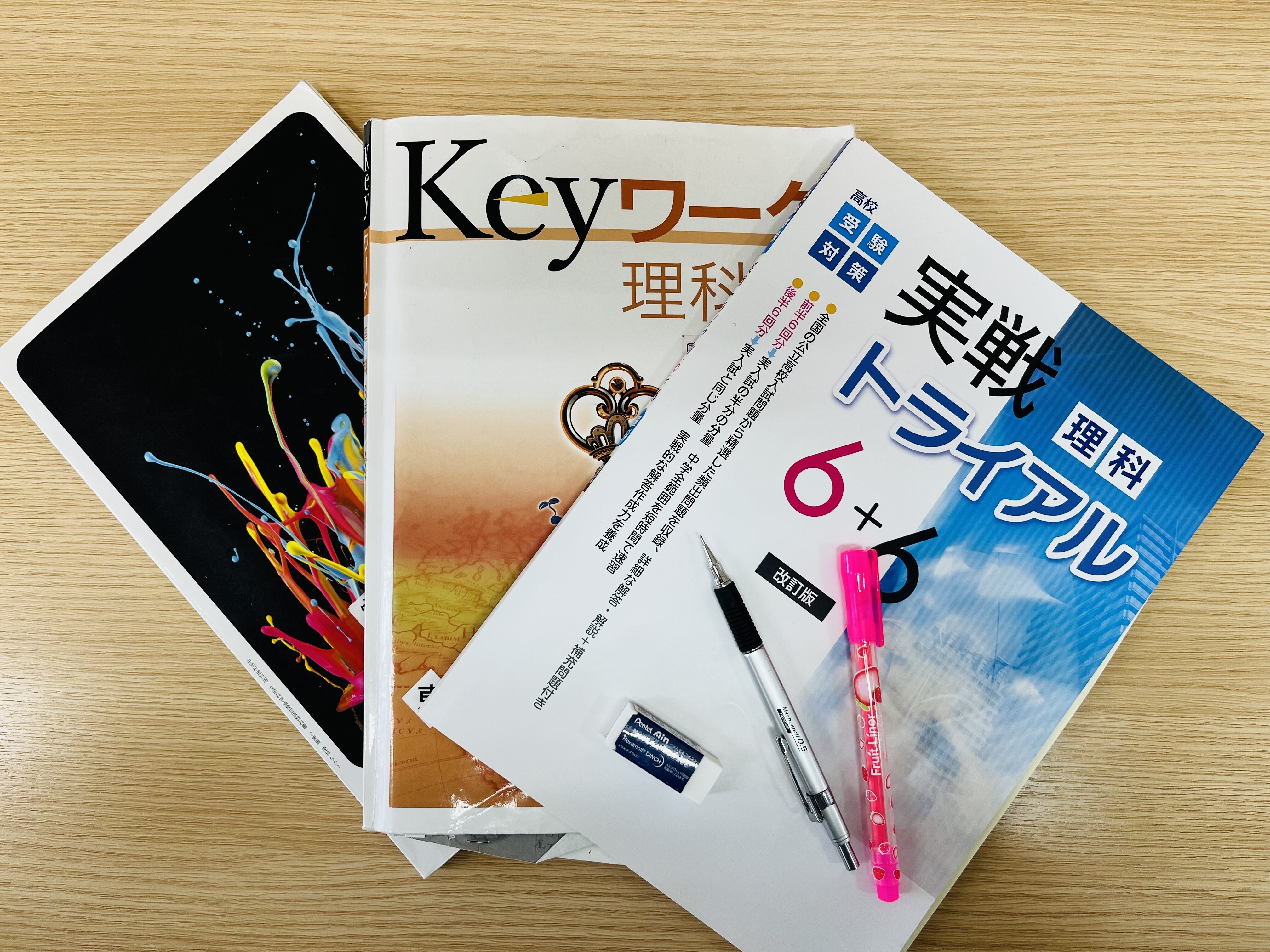
「理科の記述問題が苦手…」「答えは分かるのに、文章にすると上手くまとまらない…」 このように記述問題が解けないと悩んでいる中学生は多いのではないでしょうか?
理科のテストでは、「〇〇のしくみを説明しなさい」「なぜ△△が起こるのか説明しなさい」など、文章で答える記述問題が頻出します。 しかし、苦手な人に共通するのは、
- 何を書けばいいのかわからない
- 答えのヒントはわかるが、文章にできない
- 自分の言葉で説明するのが難しい
といった悩みです。
ですが、理科の記述問題には答えをスムーズに書くための「型」があります。 今回の記事では、記述問題がスラスラ書けるようになるためのコツや勉強法、実際の問題を使った解答例を詳しく解説します。
理科の記述問題を解くための3つの基本ルール

理科の記述問題は、「なぜ?」「どのように?」といった問いに対して、科学的な理由や仕組みを説明する問題です。
文章を書くのが苦手な人でも、この3つのルールを意識するだけで、解答が作りやすくなります!
設問の意図を正しく読み取る
まず、問題文が何を求めているのかを正しく理解することが重要です。 記述問題の聞かれ方には、大きく分けて3つのパターンがあります。
| 設問のタイプ | 求められる説明 |
|---|---|
| 「なぜ?」 | 原因と理由を説明する |
| 「どのように?」 | しくみや過程を説明する |
| 「どうなる?」 | 結果を説明する |
【例題】
- 「なぜ水に浮かぶ物体の体積が増えると浮力も大きくなるのか?」
- 「浮力の仕組み」について説明が必要
- 「光合成はどのようにして行われるか?」
- 「光合成の仕組みと流れ」を説明する
- 「塩酸に鉄を入れると、どうなるか?」
- 「鉄が溶ける原因や発生する物質」について説明が必要
解答の「型」を使って整理する
理科の記述問題では、一定の「型」を使うと、解答がスムーズに書けるようになります。
理科の記述の型
- 原因:「〇〇の性質により、△△が起こる。」
- しくみ:「□□が働くことで、△△が進行する。」
- 結果:「その結果、△△となる。」
この「型」を使うことで、「何から書けばいいのかわからない…」という悩みが解決できます。 また、「なぜ?」と聞かれたら「原因+結果」、「どのように?」と聞かれたら「しくみ」を中心に説明するなどの工夫も大切です。
いきなり書かずに、メモで整理する
記述問題が苦手な人は、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずメモを作るのがおすすめです。
【例題】「水に浮かぶ物体の体積が増えると、浮力はどうなるか説明しなさい。」
メモの整理例
- 「浮力とは何か?」 → 物体が押しのけた水の体積によって決まる(アルキメデスの原理)
- 「体積が増えるとどうなる?」 → 押しのける水の体積が増える → 浮力も増える
このように考えを整理してから「型」に当てはめて書くと、スムーズに文章を作ることができます!
実際の問題で記述の書き方をマスターしよう!
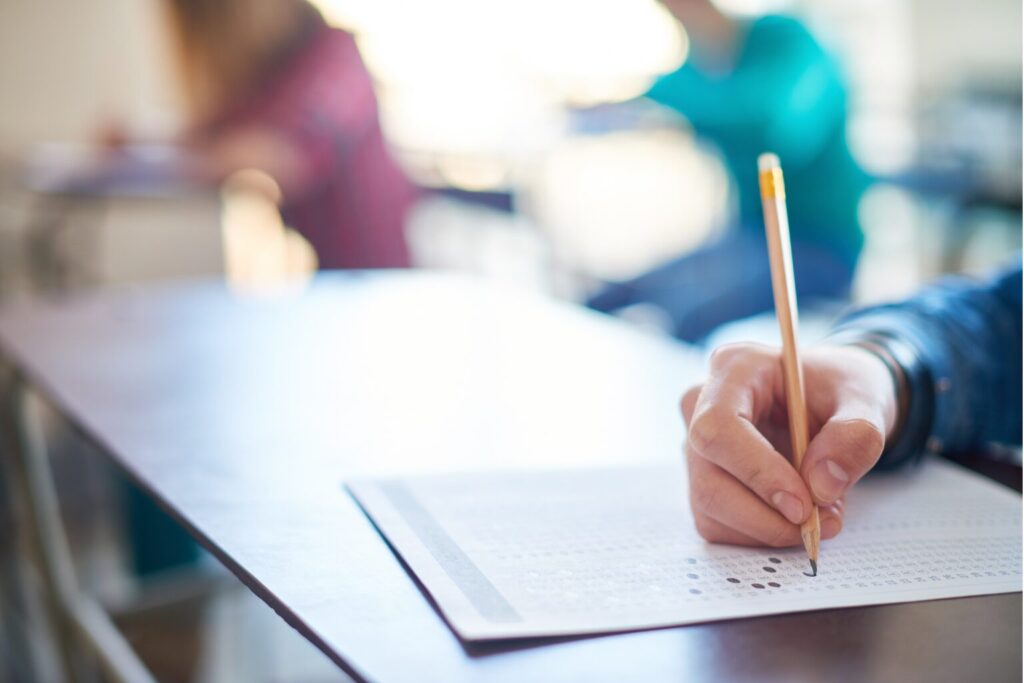
【例題1】
「水に浮かぶ物体の体積が増えると、浮力はどうなるか説明しなさい。(50字程度)」
解答例
- 原因:「浮力は、物体が押しのけた水の体積に比例する。」
- しくみ:「体積が増えると、より多くの水を押しのける。」
- 結果:「その結果、浮力も大きくなる。」
解答のポイント
- 専門用語を正しく使う!
→ 「浮力」「比例」「体積」など、物理の用語を意識的に使うことで、説得力のある解答になります。 - 因果関係を明確にする!
→ 「〇〇すると△△になる」という流れを意識して書くと、論理的でわかりやすい解答になります。 - 浮力の性質を理解する!
→ 浮力は「押しのけた水の体積に比例する」というアルキメデスの原理を踏まえて説明することが重要!
解答を詳しく分解してみよう!
- 「浮力は、物体が押しのけた水の体積に比例する。」
→ 浮力の大きさは、物体が水中に押しのけた水の量に影響される。 - 「体積が増えると、より多くの水を押しのける。」
→ 物体が大きくなると、それに伴い水中に沈む部分も増え、水をより多く押しのける。 - 「その結果、浮力も大きくなる。」
→ 押しのける水の量が増えることで、浮力も比例して大きくなる。
【例題2】
「光合成のしくみを説明しなさい。(50字程度)」
解答例
- 原因:「植物は葉の細胞にある葉緑体で光合成を行う。」
- しくみ:「光のエネルギーを使って、水と二酸化炭素からデンプンを作る。」
- 結果:「その結果、酸素を放出し、エネルギーを蓄える。」
解答のポイント
- 「光合成=デンプン+酸素ができる」ことを明確にする!
→ 光合成の基本式は「二酸化炭素+水+光エネルギー → デンプン+酸素」なので、これを要約して説明する。 - 重要な単語をしっかり使う!
→ 「葉緑体」「光エネルギー」「二酸化炭素」など、光合成に関わるキーワードを正しく使うことが大切。 - 「〇〇によって△△が起こる」の形で説明する!
→ 「光のエネルギーによってデンプンを作る」など、プロセスを明確に書く。
解答を詳しく分解してみよう!
- 「植物は葉の細胞にある葉緑体で光合成を行う。」
→ 葉緑体は光合成を行う細胞小器官で、葉の細胞に多く含まれている。 - 「光のエネルギーを使って、水と二酸化炭素からデンプンを作る。」
→ 植物は太陽光をエネルギーとして利用し、水(根から吸収)と二酸化炭素(気孔から吸収)を材料にして、デンプンを合成する。 - 「その結果、酸素を放出し、エネルギーを蓄える。」
→ 光合成の副産物として酸素ができる。また、作られたデンプンは植物の成長に使われるエネルギー源となる。
記述問題が得意になる勉強法!

記述問題は、単に知識を持っているだけではなく、論理的に説明する力が求められます。
そのため、解答の型を理解し、実際に書く練習を繰り返すことが重要です。
ここでは、記述問題を得意にするための具体的な勉強法を詳しく解説します!
1日1問、記述問題を解いてみる!
なぜ毎日1問解くのが効果的なのか?
- 記述問題は、1回や2回の練習ではなかなか上達しません。
- 毎日少しずつ取り組むことで、思考力・表現力を自然と鍛えることができる!
- 1日1問なら負担も少なく、継続しやすい。
取り組み方のポイント!
- 時間を決めて解く
→ 例えば「夕食後に1問」「寝る前に1問」など、習慣化することが大事! - 学校や塾の問題集を活用する
→ 教科書や過去のテスト問題、模試の問題から記述問題をピックアップ! - 解答後に見直しをする
→ 書いた解答と模範解答を比較して、「何が足りなかったか」を振り返る。
解答を見て、「型」に当てはめて覚える!
記述問題の基本の型!
記述問題は、大きく3つの流れで構成すると分かりやすくなります!
- 原因:「〇〇だから」
- しくみ:「〇〇の結果、△△になる」
- 結果:「そのため、□□になる」
例題:「水に浮かぶ物体の体積が増えると、浮力はどうなるか?」
- 原因:「浮力は、物体が押しのけた水の体積に比例する。」
- しくみ:「体積が増えると、より多くの水を押しのける。」
- 結果:「その結果、浮力も大きくなる。」
➡ この「型」を意識しながら練習すると、どんな記述問題でも対応しやすくなる!
型を覚える勉強法!
- 模範解答をチェックし、解答の流れを分析する!
→ 「どういう順番で書かれているか?」を意識しながら読む。 - 実際に「型」を意識して書いてみる!
→ 「原因→しくみ→結果」の流れを意識して、同じ問題を自分の言葉で書き直してみる! - 「型」を意識しながら違う問題にも挑戦!
→ どんな問題でも「型」に当てはめて考える練習をする!
専門用語を意識して、説明の精度を上げる!
なぜ専門用語が大事なのか?
- 「浮力」「葉緑体」「光エネルギー」「二酸化炭素」 など、専門用語を使うことで、解答の正確性が増す!
- 採点基準では、「正しい専門用語を用いているか」が評価のポイントになることが多い。
- 逆に、専門用語を使わずに説明すると「曖昧な解答」になってしまい、減点される可能性が高い。
専門用語を身につける方法!
- 教科書・問題集の解答をチェック!
→ どんな単語が使われているのかを意識しながら読む。 - 専門用語リストを作る!
→ 「記述問題によく出る単語」をノートにまとめ、覚えておく。 - 専門用語を使う練習をする!
→ 記述問題を書くとき、できるだけ専門用語を意識的に入れる!
まとめ

理科の記述問題が苦手でも、コツをつかめば確実に克服できます。
重要なのは、「型」に当てはめて論理的に説明すること。
そして、日々の練習を積み重ねることです。
最初はうまく書けなくても、繰り返し挑戦することで確実に上達します。
ポイントは、
- 理科の記述問題は「型」に当てはめると書きやすい!
- 「原因→しくみ→結果」の順番で説明する!
- いきなり書かずに、メモで整理してから解答を作る!
少しずつでもいいので、自分のペースで取り組んでいきましょう。
記述問題を克服すれば、理科の得点が大幅にアップし、自信を持って試験に挑めるようになります!
今日から一歩ずつ、確実に成長していきましょう!








