【大学入試 英語長文対策】関西大学の実践問題から学ぶ!和訳力を高める英文解釈の極意
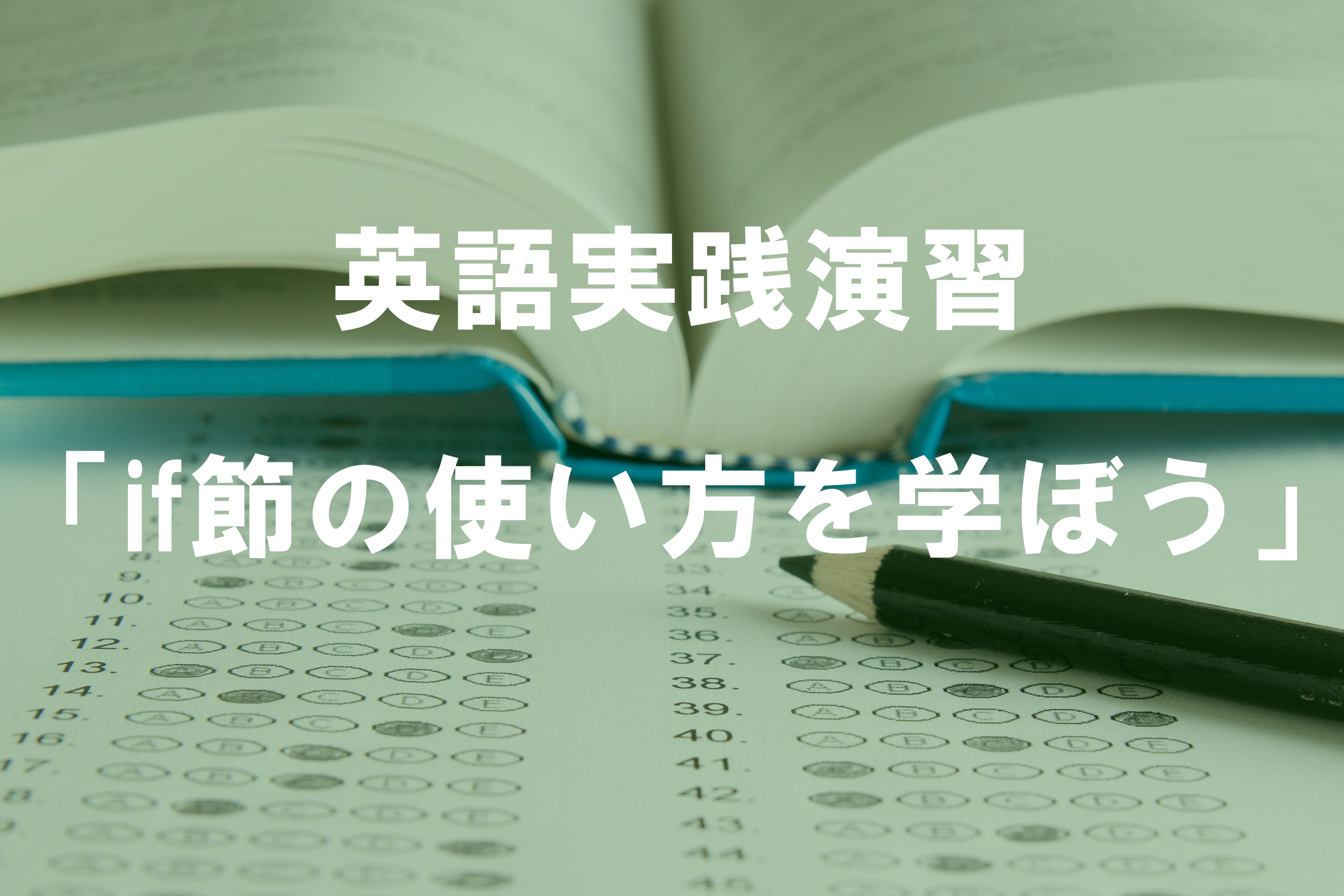
こんにちは、たっくん先生です!
今回は実際に関西大学の入試問題として出題された英文を例に、英文解釈や和訳の手順をわかりやすく解説します。
英語が苦手…という方も、文法と構文のポイントさえ押さえれば、スラスラ訳せるようになります。
根気よく進めていきましょう!
対象英文と大まかな意味
この英文を和訳することで、以下の力が身につきます。
- 条件節(if)の扱い
- 倒置表現と not only … but also … の構造
- 前置詞の正しい訳し方
- 主節の動詞を見つける力
ステップ①:if節を正しく理解する
まず、最初の節を取り出します。
英語を読むときは、まず主節の動詞(V)を見つけることが大切です。
今回の文では、”If” という接続詞から始まる節があり、これが条件節を作っています。
「want」がこの節の動詞です。「become」は「to become」という不定詞の形で出てきており、wantの目的語になっています。
和訳例:「もし本当に国際人になりたいならば、」
つまり、ここから後半部分が「条件を満たす場合に○○しなければならない」という主節に繋がります。
ステップ②:主節の動詞を探す(倒置に注意!)
次の部分が主節になりますが、ここで登場するのが英語の文法でよく出てくる構文「not only A but also B」。
さらに今回は、not only が文頭に来ているため「倒置」が起きています。つまり、
という形になっているのです。
文法に慣れていないと戸惑うかもしれませんが、ポイントはこの「do you have to grasp」が実は「you have to grasp」と同じ意味になるということです。
和訳例: 世界的な視野をもって物事を捉えるだけではなく、
ステップ③:冒号(:)の意味を理解してBを訳す
この文の面白いところは、「:(コロン)」が使われている点です。
コロンは「つまり」「すなわち」といった意味合いで使われ、前の内容を補足・説明する役割を持ちます。
こちらが「but also」のBの部分にあたり、「さらに必要なこと」を述べています。
- need:必要とする
- the ability:能力
- to respond positively:積極的に対応すること
- to regional differences in culture:文化における地域差に対して
和訳例: 文化における地域的な違いに積極的に対応する能力も必要だ
完成した和訳
全体を通して訳すと、以下のようになります。
もし本当の国際人になりたければ、世界的な視野をもって物事を捉えるだけではなく、文化における地域的な違いに積極的に対応する能力も必要です。
英文を訳すときのアドバイス
この一文には、「英文を訳す」という作業の中にある多くの大切な要素が詰まっています。
- 条件節と主節の区別
- 倒置構文の理解
- 前置詞(with、to)の自然な訳し方
- コロンの意味
これらを丁寧に押さえながら読むことで、読解力と和訳力は確実に上がっていきます。
最初は「難しいな」と感じるかもしれませんが、英文の構造をしっかり分解していけば、必ず意味は見えてきます。
和訳は“文法知識”と“文の流れを読むセンス”の両方が必要なので、数をこなして慣れていくことも大切です。
英文解釈力を伸ばす練習方法
- 条件節(if節)+主節の英文をたくさん読む
- not only構文や倒置表現がある例文を意識的に集める
- 前置詞(with, to, in, for など)の訳を複数覚えて比較する
- 実際の入試問題(関関同立・関西大学など)で演習する
まとめ
英語の和訳は、「主節の動詞を見つける」+「構文(接続詞/倒置/並列構造など)を把握する」+「前置詞の意味を意識する」ことが鍵です。
今回の例文のように、一文を丁寧に読み解くことで、自然な和訳力と解釈力を着実に身につけられます。
英語の勉強は積み重ねが大切です。焦らず、じっくり取り組んでいきましょう!
次回も引き続き入試問題を題材に、実践的かつわかりやすい解説をお届けします。
またお会いしましょう!








