「勉強したくない」の正体は?中学生300人の調査でわかった“3つの学習コスト”とは

「勉強にやる気が出ない」「うちの子、すぐに“もう無理”って言うんです」――
こうした声の裏には、単なる怠けではない“理由”が隠れているかもしれません。
2025年に発表された教育心理学の研究(真鍋一生・中谷素之)では、中学生約300名を対象に「勉強がつらく感じる理由=学習コスト」を分析し、その“しんどさ”が「機会コスト」「努力コスト」「心理コスト」の3種類に分かれることが明らかになりました。
この記事では、最新の研究結果をもとに、子どもたちが勉強に向かえない理由を見つめ直しながら、家庭や教育の現場でできる対応のヒントをお伝えしていきます。
勉強の「しんどさ」は3種類ある!|3つの“コスト”
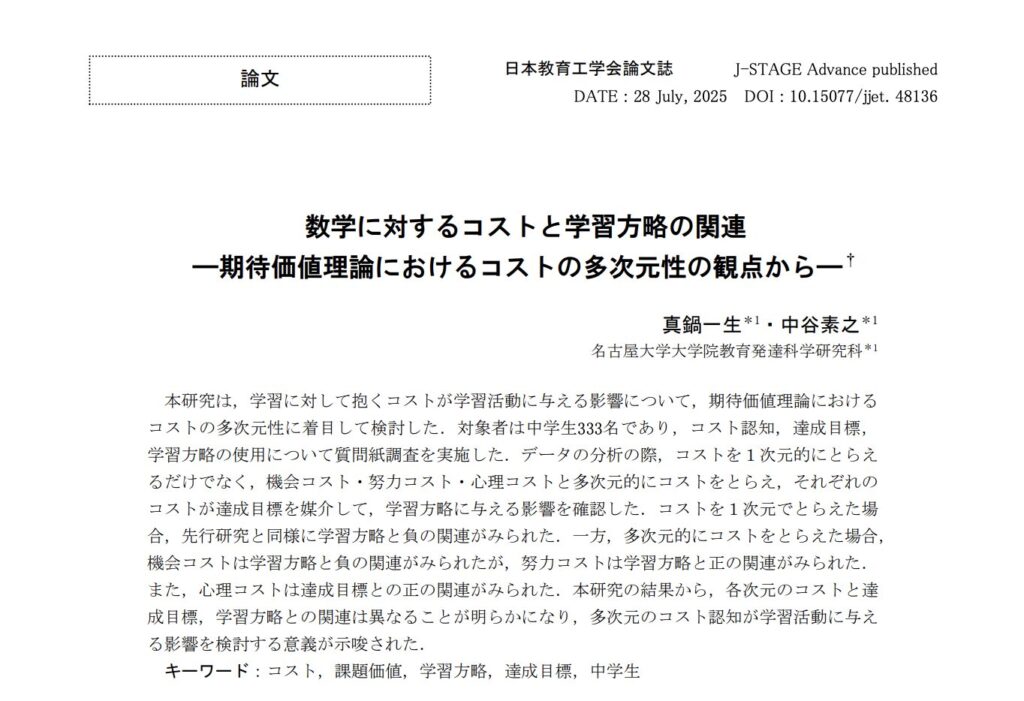
「勉強がイヤ」「やる気が出ない」という言葉の裏側には、単なる怠けではなく、本人にとっての“負担感”が隠れている場合があります。
こうした「しんどさ」は、心理学の研究において「学習コスト」と呼ばれ、3つのタイプに分けて考えることができるとされています。
それぞれのコストがどんな感覚なのか、詳しく見ていきましょう。
機会コスト|「他のことができない」がつらい
まず1つ目は、「機会コスト」です。これは、勉強をしている間に“他のことができない”ことへのストレスを指します。
たとえば、「スマホを見たいのに見られない」「ゲームの時間がなくなる」「友達と遊びに行けない」など、本来自分がやりたいこと・楽しみにしていたことが“勉強のせいで奪われている”と感じるときに生じます。
この機会コストが高くなると、「なんで勉強しなきゃいけないの?」「今やる意味ある?」という不満や抵抗感が生まれやすくなります。
努力コスト|「勉強そのものが大変」だと感じる
2つ目は、「努力コスト」です。これは、勉強そのものに感じる“きつさ”や“疲れ”の感覚です。
「問題が難しくて進まない」「覚えることが多すぎる」「理解に時間がかかる」「集中が続かない」――そういったときに、「勉強はつらいものだ」という感覚が強くなります。
この努力コストが高いと、「わかっていてもやる気が出ない」「やらなきゃいけないけど、腰が重い」といった状態になりやすく、結果として先延ばしや習慣化の妨げになります。
心理コスト|「失敗したらどうしよう」が怖い
3つ目は、「心理コスト」です。これは、勉強をすることで生じる“不安やプレッシャー”に関係しています。
「間違えたら恥ずかしい」「できないと思われたくない」「また叱られるかもしれない」――こうした気持ちは、多くの子どもたちが心の奥で感じているものです。特に完璧主義だったり、周囲の評価を気にする子ほど、この心理コストは高くなります。
心理コストが大きいと、失敗を恐れて「最初からやらない」「適当に答えてごまかす」などの行動につながることもあります。
「やる気がない」のではなく「負担が大きい」だけかもしれない
このように、子どもが「勉強したくない」と感じる理由は、やる気の有無だけでは説明できないことがわかります。
大切なのは、「何がつらいのか?」「どんなコストが高くなっているのか?」を丁寧に見極めること。
その理解が、正しい声かけや支援の第一歩になります。
驚きの結果!努力はむしろ“いい影響”を与える

「勉強がつらい」と感じる理由のひとつに、“努力コスト”があります。たとえば「難しくてついていけない」「集中がもたない」「すぐ疲れる」といった、勉強に対して必要以上にエネルギーがかかると感じることです。
こうした感覚を抱く子どもは、「やっぱりやる気がないんだろうな」と思われがちです。しかし、今回紹介している研究では、この“努力コスト”に関して驚くような結果が示されました。
努力が「ある=ダメな状態」ではなかった
研究では、中学生およそ300人を対象に、コストと学習の取り組み方の関係を調べました。
その結果、「努力コストが高い=マイナス」とは言えないことが明らかになったのです。
具体的には、努力が必要だと感じている生徒ほど、
- 計画的に学習を進める
- 内容を深く理解しようとする
- 自分の学び方を振り返る
といった、“質の高い学習方略”を使っている傾向が強いことがわかりました。
「努力している自分を肯定できるか」がカギ
この結果は、「努力を必要と感じている子どもほど、勉強に対して前向きに取り組んでいる」ということを示しています。
つまり、「大変だ」と感じること=悪いことではないのです。
むしろ、「努力している自分をどう捉えるか」が大きな分かれ目になります。
- 「努力してるのに全然できない…」と感じれば、やる気は下がっていきます。
- 一方で、「努力は必要なプロセス」「成長の途中だ」と思える子は、前向きに学習を続けていけるのです。
このように、努力コストはやり方次第で“学びの土台”に変わる可能性を秘めているのです。
“努力は報われる”を伝えるために
子どもが「勉強は大変」と感じているとき、私たち大人はそれを“悪いこと”として見るのではなく、“乗り越えるべきハードル”として扱う視点が大切です。
「難しいって感じるのは、それだけ頭を使ってるってことだよ」
「大変でも続けられるのはすごい力だよ」
そんな声かけひとつが、子どもの努力を前向きなエネルギーに変えていきます。
学びの質を上げるには?コストとうまく付き合う方法
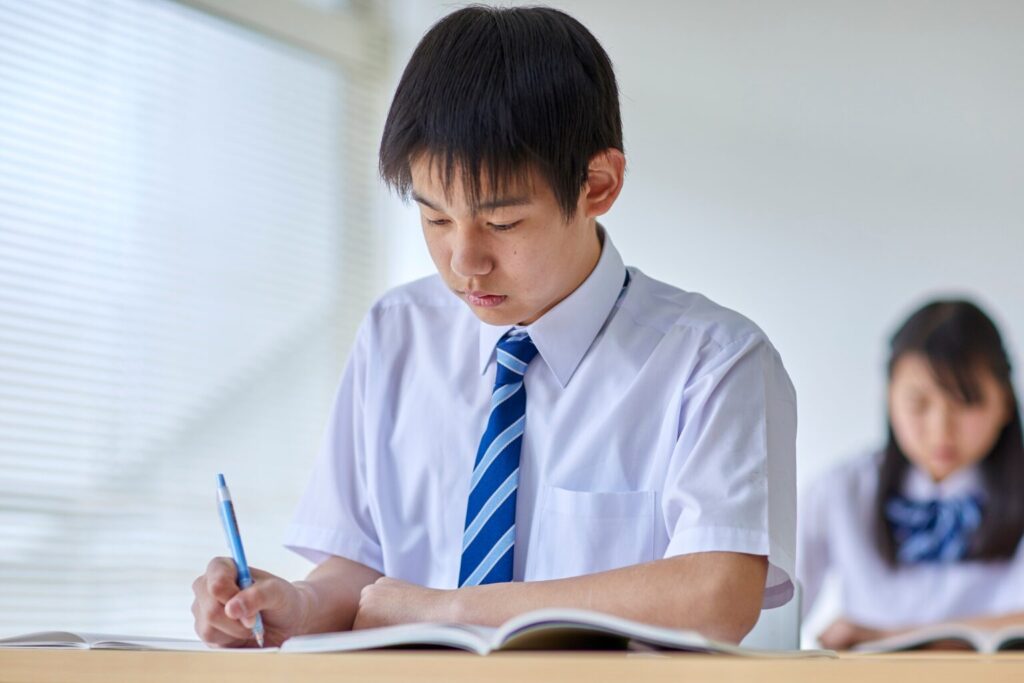
勉強に向き合ううえで、子どもたちはさまざまな“コスト”――つまり、心の負担やストレス――を感じています。
それを「やる気の問題」と決めつけるのではなく、どう向き合い、どう乗り越えていくかが、学びの質を大きく左右します。
このセクションでは、それぞれのコストとうまく付き合うための考え方と工夫をご紹介します。
機会コストには「見通し」と「短時間集中」が有効
「本当は遊びたいのに、勉強がある…」
このように感じているときは、勉強が“楽しみを奪う存在”のように思えてしまいます。そんなときに効果的なのが、「勉強の見通し」を立てることです。
- どれくらい時間がかかるか
- どこまでやれば終わるか
- 終わったら何ができるか
こうした情報が明確になるだけでも、「終わりが見えるからやってみよう」という気持ちにつながりやすくなります。
さらに、「○分だけ集中してやってみよう」といった短時間のチャレンジも有効です。10分間だけ集中して取り組むだけでも、「自分はやれる」という感覚が得られ、次の行動につながります。
努力コストは「成長の証」と捉える視点を
「難しくて時間がかかる」「すぐに疲れてしまう」――努力コストが高いと、どうしても学習は“つらいもの”に感じられます。
けれども、努力を要すること=悪いことではありません。
むしろ、それは「脳がしっかり働いている証拠」「成長しているからこそ感じる負荷」でもあります。
大切なのは、その努力を本人が前向きに捉えられるようにすることです。
- 「できることが増えてきたね」
- 「前より速く解けたじゃん」
- 「この問題に取り組んでるの、すごいことだよ」
こうした声かけで、努力の意味を実感できれば、コストは“障害”ではなく“挑戦”として受け入れられるようになります。
心理コストには「失敗しても大丈夫」という安心感を
間違えることや失敗することが怖くて、勉強から距離を置いてしまう――それが心理コストの影響です。
このコストに対処するには、「失敗しても安全な場所」だと感じられる環境づくりが必要です。
たとえば、
- 答えが合っていなくても「挑戦したこと」を評価する
- 「間違いは成長のきっかけになる」と日頃から伝える
- 周りと比べず、本人の変化や努力を見てあげる
といった関わり方は、心理的な安心感を少しずつ高めてくれます。
また、テストや小テストでも「やり直しのチャンスがある」ことを伝えることで、「一発勝負で失敗したら終わり」というプレッシャーを和らげることができます。
コストは“消す”のではなく、“理解して付き合う”もの
勉強に感じるしんどさは、無理にゼロにしようとしなくても構いません。
大切なのは、「どのコストが強くなっているのか」を理解し、その子に合った支え方をしていくことです。
- 何が負担に感じているのか?
- どんな場面でやる気を失いやすいか?
- どんなときなら前向きになれるのか?
そうした視点を持つことで、子ども自身も「自分のしんどさ」を言葉にできるようになり、勉強との付き合い方が変わっていきます。
“やる気がない子”を理解する新しい視点

勉強に取り組まない子どもを見ると、「やる気がない」「自分からやろうとしない」と感じることがあります。
でも、本当に“やる気がない”のでしょうか?
もしかすると、その裏には、「見えないしんどさ」=コストが隠れているかもしれません。
「やらない」のではなく「できない理由がある」
子どもが勉強を避けるとき、その行動には意味があります。
たとえば、ノートを開かない、課題を出さない、テスト勉強を後回しにする――それらは単なる怠けではなく、機会・努力・心理のどれかのコストが高くなっているサインかもしれません。
- やる時間はあるのにやらない(→ 機会コストが高い)
- 問題に向かってもすぐに疲れる(→ 努力コストが高い)
- 間違えるのが怖くて問題を開けない(→ 心理コストが高い)
このように、「やる気がない」のではなく、“やれない理由”がある状態と捉えることで、見える風景が変わってきます。
声かけや関わり方も変わってくる
「やりなさい」と命令する前に、「どこがつらい?」「何が気になってる?」と聞いてみる。
そんな一言が、その子の心を開くきっかけになります。
また、励ましの言葉も、“努力を認める”タイプのものが有効です。
- 「ここまでやろうと思っただけですごいね」
- 「前より自分で進められるようになってきたね」
- 「難しいのに、ちゃんと向き合ってるね」
こうした声かけは、本人が自分の努力や工夫を実感し、「自分にもできる」と思えるきっかけになります。
「やる気を引き出す」とは、心の重りを取りのぞくこと
多くの場合、子どもたちは「やりたくない」のではなく、「やれる状態じゃない」のです。
やる気を引き出すというのは、何かを“足す”のではなく、“引いてあげる”ことが必要な場面もあるということ。
- 過度なプレッシャー
- 成功への完璧なイメージ
- 比較や評価への不安
こうした“心の重り”をそっと軽くするだけで、子どもは自然と前を向きはじめます。
まとめ|“しんどさ”を理解することが学びの第一歩
「やる気がない」「集中しない」「続かない」――
勉強に対するネガティブな反応は、子どもたちにとって日常の中でよくあるものです。
しかし、今回ご紹介したように、その背景には“コスト”という3つのしんどさが隠れているかもしれません。
- 他のことを我慢しなければいけない「機会コスト」
- 理解や継続にエネルギーが必要な「努力コスト」
- 失敗や評価が怖いと感じる「心理コスト」
このような負担は、どれも子どもたちの中では無意識に「勉強から距離をとりたい」という行動に変わって現れることがあります。
つまり、「やる気がないように見える」のは、その子なりの“自己防衛”かもしれないのです。
だからこそ、周りの大人がまずできることは、「なぜ今、勉強に向かえないのか?」を一緒に考えてみること。
「どこが大変に感じているのか?」「何が不安なのか?」――そうした視点で子どもに寄り添うことが、学びの第一歩になります。
そしてもうひとつ、大切にしたいのは、「努力が必要だ」と感じている子どもほど、深い学びに向かおうとしている可能性があるということ。
“つらい”は“がんばっている証拠”かもしれません。
勉強が思うように進まないときほど、その子が感じている“しんどさの正体”に目を向けてみてください。
そこから、学びに向かう道は、少しずつ開けていくはずです。
【参考文献】真鍋一生・中谷素之「数学に対するコストと学習方略の関連―期待価値理論におけるコストの多次元性の観点から―.日本教育工学会論文誌.https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjet/advpub/0/advpub_48136/_pdf/-char/ja








