【2025年改訂】次期学習指導要領で子どもの学びはどう変わる?保護者が知っておきたい教育改革のポイント

2025年9月5日、文部科学省は次期学習指導要領の改訂に向けた重要な方針を示す「論点整理(素案)」を公表しました。これは、これからの子どもたちの学びや学校生活がどのように変化していくのかを示す“地図”のようなもので、全国の学校教育に大きな影響を与える内容です。
今回の改訂では、「情報活用能力の育成」「柔軟な教育課程」「探究学習の質の向上」「学習評価と入試の見直し」など、これまで以上に“個別最適な学び”や“自律的な学び”を重視する方針が打ち出されました。
保護者の皆さまにとって、「学校の授業がどう変わるのか」「わが子の学びはどうサポートすればよいのか」は、とても気になるテーマだと思います。この記事では、発表された内容をもとに、押さえておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
- 「学習指導要領ってよく聞くけど、正直よくわからない…」
- 「子どもたちの授業がこれからどう変わるのか知っておきたい」
- 「大学入試や評価の仕組みが変わるって本当?」
- 「今のうちから家庭でできることがあれば知りたい」
学習指導要領ってそもそも何?
「学習指導要領」という言葉、ニュースなどで聞いたことはあるけれど、具体的にはよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。
学習指導要領とは、全国どの地域の子どもたちも一定の教育を受けられるようにするための「国が定めたカリキュラムの基準」のことです。言い換えると、「全国共通の学校教育の設計図」です。
この指導要領に基づいて、教科書が作られ、学校の授業内容や時間配分が決まります。つまり、私たちの子どもたちが「学校で何をどのように学ぶか」を決めているのが学習指導要領なのです。
どうして見直されるの?
時代が変われば、社会に必要とされる力も変わっていきます。たとえば、今の子どもたちは「AI」「情報化社会」「グローバル化」といった新しい時代を生きていくことになります。
そこで文部科学省は、こうした時代の変化に対応するために、おおむね10年ごとに学習指導要領を見直しているのです。
現行の指導要領は2020年度から小学校で導入されたものですが、それもすでに見直しが始まっており、次の世代の教育の方向性を定める議論が本格化しています。
今回の改訂で大切にされる3つの考え方
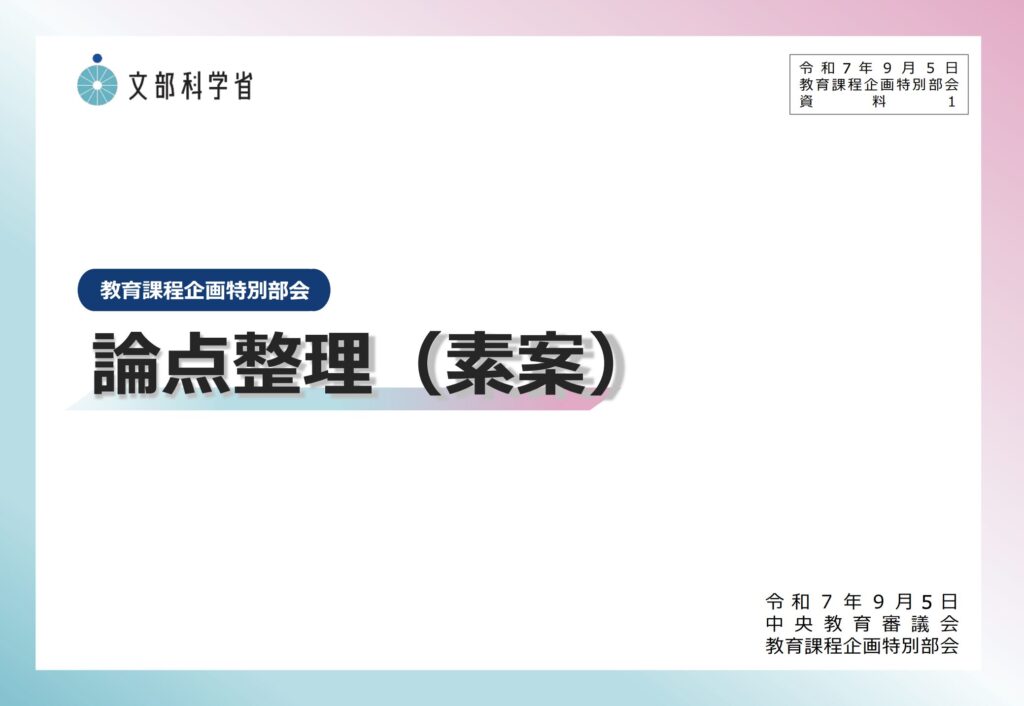
次期学習指導要領の改訂では、時代の変化に対応し、子どもたちが将来を生き抜くために必要な力を育むことが重視されています。その中でも特に強調されているのが、次の3つの基本的な考え方(方向性)です。
① 情報活用能力の強化(読み書き・計算+情報リテラシー)
現代は、インターネットやAIがあふれる「情報社会」。子どもたちには、正確な情報を見分け、必要な情報を活用し、表現・発信する力が求められています。これまでの「読み・書き・計算」に加えて、情報の読み取り・発信・活用する力=“情報活用能力”をしっかり育てていくことがポイントになります。
② 柔軟で個別最適な学び(全員一律からの転換)
子どもたち一人ひとりが持つ興味や学び方の違いを尊重し、それぞれに合った学び方ができるようにすることも大切な視点です。これまでは「全員が同じ授業を同じペースで受ける」のが一般的でしたが、今後は「子どもに合わせて学び方を柔軟に変える」取り組みが重視されていきます。
ICT(タブレットやデジタル教材)を活用した個別学習などが、その一例です。
③ 探究的な学び・思考力の育成(暗記から思考へ)
これからの教育では、「答えを早く出す」ことよりも、「なぜ?どうして?を考える力」が重視されます。教科ごとに学んだ知識をつなげ、自分なりの考えを深めたり、他者と議論したりするような“探究的な学び”が増えていきます。受け身ではなく、自ら問いを立てて学ぶスタイルが主流になっていくのです。
これら3つの考え方は、将来、子どもたちが社会で活躍するために欠かせない「生きる力」を育むことを目的としています。つまり、学びの中身も、学び方も、大きくアップデートされるということなのです。
ご家庭でもぜひ、「なぜこれが必要なんだろう?」「どうやって調べたの?」など、日常の中で問いかける習慣を大切にしていきましょう。
ポイント① 情報活用能力の強化

次期学習指導要領で最も重要な柱の一つが、「情報活用能力の強化」です。これは、いわば「読み・書き・計算」に続く、これからの時代の“新しい基礎力”といえるものです。
「情報活用能力」って何?
ここでいう「情報活用能力」とは、ただパソコンやタブレットを使えることではありません。
主に以下の3つの力を含みます。
- 必要な情報を見つけ出す力
- 情報を正しく理解し、整理・分析する力
- 自分の考えとして表現・発信する力
つまり、膨大な情報の中から必要なものを選び、考え、伝える力を総合的に育てることを目指しています。
なぜ今、それが必要?
現代の子どもたちは、スマホやネットに囲まれた「情報過多の時代」を生きています。
その中で、正しい情報を見極める力や、他人と協力して情報を共有する力は、社会に出たときに不可欠です。また、AIの進化によって、ただ知識を覚えるだけの学びでは不十分になっています。
「知識を使って何をするか」が問われるようになってきたのです。
学校での取り組み例
今後の授業では、次のような活動がより重視されていきます。
- 調べ学習で信頼できる情報源を選ぶ練習
- インターネットや統計資料などを使った情報収集と分析
- スライドやレポートなどを使って自分の意見をまとめて発表する活動
これにより、単に「答えを覚える」勉強から、「答えを導き、伝える」力を育む授業へとシフトしていきます。
情報活用能力は、将来、どんな職業に就いても役立つ「生きる力」です。時代の変化に対応しながら、家庭と学校が一緒になって、子どもたちの未来を支えていきましょう。
ポイント② 柔軟な教育課程で個別対応

これからの学校教育では、「全員が同じ授業・同じスピードで学ぶ」時代から、「一人ひとりに合った学び方が選べる」時代へと変わっていきます。その中心となるのが、「柔軟な教育課程(カリキュラム)」の実現です。
どう柔軟になるの?
これまでは「全国で共通の教科書・内容・時間数」で学ぶのが基本でした。
しかし、これからは次のような形で子どもの実態に合わせた学びが可能になります。
- 学年をまたいだ学習(例:小6で中1の英語に挑戦)
- 教科や単元の順番を工夫(例:子どもの関心に応じて理科の単元を前倒し)
- 探究活動や地域学習を組み込む(例:地域の課題を調べて提案する授業)
つまり、子どもの発達段階や興味関心に応じて、時間や内容、学び方に“余白”が生まれるということです。
目的は「個別最適な学び」
この柔軟な教育課程は、文部科学省が掲げる「個別最適な学び」の実現を目指したものです。
つまり、全員に同じ学びを強いるのではなく、
- 学力や理解度に応じたサポート
- 得意分野をさらに伸ばす学習
- 苦手な単元にじっくり向き合う時間
など、一人ひとりの子どもにとって最も適した学び方を選べるようにすることが目的です。
不登校や発達特性のある子にも対応しやすく
この「柔軟な設計」は、これまで学校の枠組みにフィットしにくかった子どもたちにも希望を与える改革です。
- 不登校でもICT(タブレットなど)を使って学習継続ができる
- 発達特性のある子にも、ペースや方法を工夫して対応できる
こうした「誰一人取り残さない教育」が現実のものとなっていきます。
柔軟な教育課程は、画一的な教育から脱却し、「その子らしい学び」を実現するための第一歩です。
未来を生きる子どもたちが、自分に合ったスタイルで学べるよう、私たち大人も一緒に理解と準備を進めていきましょう。
ポイント③ 教育に「余白」をつくる

現代の学校教育は、授業時間もカリキュラムもぎっしり詰まっています。その中で、子どもたちは日々の学習、宿題、習いごとに追われ、「じっくり考える」「自分で学びを深める」余裕がないという声が増えてきました。
そんな課題を受けて、次期学習指導要領では「教育の余白」という考え方が重視されます。
そもそも「余白」ってどういう意味?
ここでいう「余白」とは、単に「空き時間」ではありません。知識の詰め込みを抑えて、子ども自身が考え、試し、創造できる時間や機会をつくるということです。
たとえば、
- 授業で学んだことを、自分なりにまとめたり、友達と議論する時間
- 興味のあるテーマについて深掘りする自由な探究の時間
- 行事や体験活動を通して「学びに向かう力」を養う余地
これらの時間こそ、学びを“自分ごと”にするチャンスなのです。
なぜ今、「余白」が必要なのか?
社会が複雑に変化するなかで、ただ知識を持っているだけではなく、「どう考えるか」「どう伝えるか」「どう動くか」が問われる時代になりました。
そのためには、次のような力が重要です。
- 自分の頭で考える力(思考力)
- 他者と協力しながら課題に取り組む力(協働力)
- 自分の考えや学びを形にする力(表現力・創造力)
こうした力は、詰め込まれた授業だけでは身につきにくいもの。だからこそ、「余白」が必要なのです。
どうやって余白をつくる?
教育の中に「余白」を取り入れるために、以下のような工夫が進められます。
- 教科の内容を整理・厳選し、本当に必要な学びに絞る
- カリキュラムの再構成で、「深める」「広げる」時間を設ける
- 子どもたちの問いや疑問を起点にした授業づくり
- 体験や対話を重視した時間の確保(例:総合的な学習の時間、探究の時間)
つまり、知識の量を減らす代わりに、学びの質と深さを高めるという考え方です。
子どもの未来に、ゆとりと創造の時間を
教育に「余白」を設けることは、学力の低下を意味するのではなく、むしろ本質的な力を育むための投資です。子どもたちが自分らしく、創造的に学ぶことのできる環境へと、学校教育は少しずつ進化しています。
その変化を、私たち大人もあたたかく受け止め、サポートしていきたいですね。
ポイント④ 探究学習の質を高める学びへ

ここ数年で、学校教育に「探究学習」という言葉がよく出てくるようになりました。総合的な学習の時間や総合的な探究の時間などで、子どもたちは「自分でテーマを決めて調べ、まとめ、発表する」活動を行っています。
しかし、現場ではこんな声も聞かれます。
- 「ネットで調べてまとめるだけで終わっている…」
- 「表面的な学習で、子どもが深く考える時間が少ない…」
そこで、次期学習指導要領では「探究の“質”を高める」ことが大きな柱のひとつとされています。
探究学習って何のためにあるの?
探究学習は、単に“知識を増やす”学びではありません。
目的は、
- 自ら問いを見つけ、考え、調べ、深めていく力を養うこと
- 答えのない課題に取り組み、他者と協働しながら解決策を見出す経験を積むこと
- 社会や人生に向き合う「学びの姿勢」を身につけること
です。
これからの社会では、マニュアル通りの正解ではなく、「自分で課題を設定し、自分の考えを形にする力」が問われます。その土台を育てるのが探究学習なのです。
今後の改革ポイント:「探究の質」をどう高めるか?
次期指導要領では、以下のような視点で探究学習の内容が見直されます。
①「問いの立て方」の力を育てる
- 子ども自身が「なぜ?」「どうして?」と感じたことから学びが始まるように。
- 教員がテーマを与えるのではなく、自分で問いを設定できるようサポート。
② 調べて終わりにしない
- 情報を集めて満足せず、「その情報から何がわかるか」「どう考えるか」まで導く。
- 比較・分析・考察など、思考のプロセスを重視。
③ 社会とのつながりを意識する
- 地域の課題やニュースなど、現実社会との接点を持たせることで、学びの実感を深める。
- 地域の人との対話やフィールドワークも活用。
④ プレゼンや対話を通して学びを広げる
- 学んだことを他者に伝える・議論する・フィードバックを受けることで、より深い学びに。
保護者として知っておきたいこと
探究学習は、「正解を教えてもらう」学びとは異なります。
その分、「うちの子はちゃんと理解できているのかな?」と不安になることもあるかもしれません。
けれど、探究学習では以下のような成長が見られればOKです。
- 自分で問いを立ててみようとする姿勢
- 最初の答えを疑って、もう一度調べてみようとする行動
- 友達と学びを共有したり、意見を言えるようになる変化
こうしたプロセスの中に、これからの社会で必要な力の芽が隠れています。
家庭でも、以下のような関わり方がおすすめです。
- 「なんでそれに興味をもったの?」と問いかけてみる
- すぐに答えを教えるのではなく、「どう思う?」と考える時間をつくる
- 子どもが調べたことや感じたことを、関心を持って聞いてあげる
「探究力」は、未来を切りひらく力
AIが進化する時代に、人に求められるのは「問いを立てる力」と「意味をつくる力」です。
探究学習は、子どもたちが自らの学びを深め、「自分の考えを持って生きる」ための土台となります。
これからの教育改革では、この探究の力がさらに重視されます。保護者としても、その意義を知り、あたたかく見守っていくことが求められます。
ポイント⑤|学習評価と入試改革の方向性

学校での成績や通知表、さらには高校・大学入試は、長年「点数=評価」という構図で成り立ってきました。
しかし、次期学習指導要領では、「どのように学んだか」や「どんな力が育ったか」といった学びのプロセスにも注目し、それを評価に反映させていく方向が打ち出されています。
なぜ「評価の改革」が必要なのか?
これまでの評価方法は、どちらかというと「正解に早くたどりついたか」を重視していました。
しかし、これからの社会では、
- 答えのない問いに向き合う力
- 自分の考えを人に伝える力
- 試行錯誤しながら進める力
…といった、目に見えにくい「非認知能力」や「学び方の力」がますます重要になってきます。
こうした力を育てるには、「評価のあり方」も変えていかなければなりません。
どんな方向に変わっていくの?
次期学習指導要領の論点整理では、以下のような学習評価と入試改革の方向性が示されています。
① 観点別評価をより丁寧に
現在の通知表では、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点が使われています。これらを今後さらにわかりやすく、「学びの成長」を具体的に伝える形で見直していく方向です。
例:単に「B」ではなく、どの力がどこまで伸びているかが言葉で伝えられるように評価する。
② ポートフォリオ(学習記録)の活用
子どもたちの活動や思考の過程、提出物などを記録として残し、テスト以外の評価材料として活用する動きが強まります。
これにより、1回のテストだけでなく、日々の学びの積み重ねが評価される仕組みに。
③ 入試のあり方も見直しへ
高校や大学の入試でも、次のような動きが始まっています。
- 思考力・表現力を問う記述式問題の導入
- プレゼンテーションや面接による評価
- 中学校では「調査書」(通知表)の観点評価の見直し検討も
保護者が知っておきたい視点
評価=通知表や点数だけではない
今後、子どもたちが学校でどんなことを考え、どう学んでいるか、その過程こそが評価対象になります。
たとえテストで高得点が取れなくても、次のような姿勢が評価される可能性があります。
- 最後まであきらめずに取り組んだ
- 考えたことをノートに丁寧に書いていた
- 友達と話し合いながら自分の意見を深めた
こうした日々の努力を見つけ、認めてあげる姿勢が、これからの保護者にも求められます。
入試も「点数勝負」ではなくなるかも
もちろん、筆記試験は今後も続きますが、それに加えて、
- 調査書の中身
- 面接や自己表現活動
- 探究活動やプレゼンの経験
…などが入試で評価される可能性が高まっています。そのためにも、普段の学び方・姿勢を大切にすることが、将来の進路にもつながっていくのです。
学習評価や入試の改革は、「今の子どもたちにとって何が本当に必要か?」を見つめ直す動きです。
点数だけでは測れない力をどう評価し、育てていくか――。
それは、子ども一人ひとりの「本当の成長」を大切にする教育への一歩でもあります。
「うちの子はテストが苦手だから…」という悩みも、評価の多様化によって、新しい希望に変わるかもしれません。家庭でも、「どう学んでいるか」に目を向け、子どもの努力や変化を温かく見守っていきましょう。
その他の注目点

次期学習指導要領に向けた改革では、主要な5つの論点のほかにも、学校現場や子どもたちの未来に関わる重要な視点がいくつか挙げられています。ここでは、その中でも特に注目すべきポイントを3つご紹介します。
教師の負担軽減と教育の質の向上
近年、学校現場では教員の多忙化が大きな課題となっています。次期改訂では、教員の働き方改革も大きなテーマの一つとして位置づけられています。
- 授業準備・教材研究の時間確保
- チームで支える学校づくり
- 教職員の専門性向上とサポート体制の強化
これにより、教師一人ひとりが「子どもと向き合う時間」を増やし、より質の高い授業や支援ができる環境整備が進められる見通しです。
幼児教育・初等教育とのつながり
新たな学びの枠組みは、小・中・高校にとどまらず、幼児教育との連続性も意識されています。就学前から「遊びや体験を通じて学ぶ力」を育み、小学校以降の学びへ自然につなげていく取り組みが強調されています。
今後は「小1プロブレム」などへの対応にもつながる形で、子どもの発達段階に応じた教育の一貫性がより重視されていくと考えられます。
地域との連携や社会とのつながり
探究学習やキャリア教育の充実に伴い、学校と地域、社会との連携もますます重要になります。
- 地元企業や団体と連携した「実社会での学び」
- 地域課題をテーマにした探究活動
- ボランティアやインターンシップなどの体験
こうした取り組みを通じて、子どもたちが「社会の一員としての自覚」や「地域への関心」を自然に育てていく仕組みが広がっていく見込みです。
保護者としての関わり方も変わる
このような教育の広がりは、学校だけでは実現できません。保護者や地域の理解・協力が、子どもたちの学びを支える大きな力になります。
行事や授業公開だけでなく、地域活動や学びの場づくりに関心を持ち、可能な範囲で関わっていく姿勢が、これからますます大切になるでしょう。
保護者が今からできること

次期学習指導要領や入試制度の見直しは、「未来の子どもたちに必要な力を育てる」ための大きな転換点です。一方で、保護者にとっては「何がどう変わるの?」「今のうちに何をすべき?」と不安に感じることも多いでしょう。
でも、大丈夫。大切なのは「すべてを理解すること」ではなく、「子どもと一緒に学び方を考える姿勢」です。
子どもの学びに寄り添う3つの姿勢
① 「点数」だけでなく「過程」を見つめる
通知表やテストの点数はもちろん気になりますが、それだけがすべてではありません。
- 「どんなふうに頑張っていたか?」
- 「どこでつまずいて、どう乗り越えようとしたか?」
- 「学びに対する姿勢がどう変わってきたか?」
こうした“見えにくい成長”にも目を向けることで、子どもは自信を持って学び続けることができます。
② 探究活動や表現の場を家庭でも応援する
次期指導要領では、「自ら課題を見つけて調べる」「自分の考えを伝える」といった探究的な学びが重視されます。
- 興味のある本を一緒に読んでみる
- 家庭での会話で「なぜ?どうして?」を大切にする
- 発表や作文を「聞いてあげる・読んであげる」
など、日常の中に学びを見つける姿勢が、学校での活動にもつながっていきます。
③ 変化に前向きな言葉をかける
制度や評価方法の変更には、子どもも不安を感じることがあります。
そんなときに「よくわからないから心配…」ではなく、
「新しい学びって面白そうだね」
「いろんな力が認められるっていいね」
といった前向きな言葉で安心感を与えることが、子どもの心の支えになります。
保護者として知っておきたいこと
- 学習指導要領は10年に一度見直される「教育の基本方針」です。
- 今回の改訂は、2020年度からの変化に続く「第2段階」とも言える動きです。
- 情報活用能力、探究力、学びの評価の見直しなど、子どもの未来に直結する重要な変化が含まれています。
- 学校任せにせず、「何を学んでいるか」「どんな力をつけようとしているか」を家庭でも共有することが鍵です。
学びの在り方が変わっても、子どもにとって一番の支えは「わかってくれる親」の存在です。
制度が変わるからこそ、子どもの努力や成長に気づき、認めてあげる目線が、今まで以上に大切になります。「正解を教える」よりも、「一緒に考える」「見守る」「応援する」姿勢が、これからの学びの時代に合った保護者の関わり方です。
今後のスケジュール
次の学習指導要領は現在、国(文部科学省)で議論が進められており、これから数年かけて段階的に準備されていきます。
まずは、2025年に国の専門部会で「どんなことを改めて考えるべきか」が整理されます。そのあとは、教科ごとに専門のチーム(ワーキンググループ)にバトンタッチされ、国語・算数・理科などの教科ごとに詳しい内容を検討する段階に入っていきます。
2026年には方向性が固まります
国は2026年(令和8年)の夏ごろまでに方針をまとめ、年内に最終的な案(=答申)を発表する予定です。この答申が、実際の「新しい学習指導要領」のもとになります。
子どもたちの学校での実施は2030年度から
新しい指導要領に基づく授業は、以下のようなスケジュールで実際に学校でスタートしていく見通しです。
| 学校の段階 | 実施が始まる年度(予定) |
|---|---|
| 小学校 | 2030年度(令和10年度) |
| 中学校 | 2031年度(令和11年度) |
| 高校 | 2032年度(令和12年度)以降 |
この実施に向けて、教科書の内容が変わったり、先生方の研修が行われたり、学校現場でもしっかり準備が進められていきます。
「教育の内容が変わる」と聞くと不安に感じる方もいるかもしれませんが、こうした改訂は時間をかけて丁寧に行われるものです。今後も、子どもたちがよりよい学びを受けられるよう、家庭と学校が一緒になってサポートしていくことが大切です。
入試改革の時期は?
- 学習指導要領の変更にともない、高校入試や大学入試の評価方法も見直しが検討されています。
- 高校入試では内申点や記述式問題、探究活動の成果などがより重視される方向に。
- 大学入試では「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」など、多面的な評価方法がさらに拡充される見込みです。
こうした入試制度の改革は、現在の中学1〜2年生、高校1年生以降の世代が対象になる可能性が高いため、今のうちから情報を整理しておくことが大切です。
“あと数年ある”ではなく、“あと数年あるからこそ準備できる”
制度の完全実施は数年先とはいえ、今のうちから少しずつ準備をしておくことで、焦らずに対応できます。
- 「学び方の変化」に家庭も慣れておく
- 「情報活用力」や「表現力」を家庭でも育てていく
- 学校の動きや説明に注目していく
このような積み重ねが、将来の教育環境の変化にしっかりと備えることにつながります。
まとめ|教育の変化を前向きに受け止めよう

- 学習指導要領は「学校で何をどう教えるか」を決めるルール。約10年ごとに見直される。
- 2025年9月発表の論点整理では、次の改訂の方向性が示されました。
- 改革のポイントは以下の5つ
- 情報活用能力の強化
- 柔軟な教育課程で個別対応
- 教育に“余白”をつくる
- 探究学習の質の向上
- 学習評価と入試改革
- 新しい学習指導要領の実施時期は、小学校=2030年度/中学校=2031年度/高校=2032年度以降 の予定。
今回の学習指導要領の改訂は、「ただの制度変更」ではなく、子どもたちの未来を見据えた“学びの在り方”の大きな転換です。AIやグローバル化が進む社会では、暗記力や正解を出す力以上に、情報を選び、考え、表現し、協働する力が求められるようになってきています。
こうした力を育てるために、教育現場ではこれから「探究学習」「個別最適化された学び」「柔軟なカリキュラム設計」など、今までにない挑戦が始まります。そしてそれは、家庭の理解とサポートがあってこそ、子どもたちの成長につながるのです。
次期学習指導要領の本格実施までには数年あります。この「準備期間」は、単なる“待ち時間”ではなく、家庭にとっても学校にとっても、じっくりと変化に対応するための“育て直しの時間”です。子どもたちが伸びる芽を信じて、学校や先生と手を取り合いながら、「未来を生きる力」をいっしょに育てていきましょう。








