理科の計算問題で手が止まる?「物質の変化」単元のつまずきと克服法を徹底解説!

「理科の計算問題になると、急に手が止まってしまう…」
そんな悩みを抱える中学生は、決して少なくありません。
特に「物質の変化」単元では、知識を問う問題とあわせて質量や体積などの計算問題、実験データの読み取りが多く出題され、苦手意識を持ちやすい単元の一つです。
しかし、こうした計算問題には“よくある解き方のパターン”が存在し、正しいステップで学び直すことで必ず克服できる分野でもあります。
この記事では、
- 計算問題が苦手な理由
- どのように学び直せば「できる」ようになるか
- 櫻學舎で行っている具体的なサポート
を丁寧に解説していきます。
苦手なまま放置せず、“できる自分”に変わるきっかけをここから掴んでいきましょう。
理科の計算問題が苦手でも、正しい学び方で必ず克服できる!
理科の「物質の変化」単元では、質量や体積、反応比などを用いた計算問題が頻出です。
そして多くの中学生が、用語や知識は覚えていても、計算になると手が止まってしまうという悩みを抱えています。
「数字が出てきた瞬間に頭が真っ白になる」
「式をどう立てていいか分からない」
「表やグラフを見ると、どこに注目すればいいのか分からない」
──こうした声は、塾の現場でも日常的に聞かれます。
でも安心してください。
理科の計算問題は、正しい順序で理解を深めていけば、必ず解けるようになります。
なぜなら、理科の計算問題は「ひらめき」ではなく、
知識 → 理解 → 手順の再現という積み重ねで解ける構造だからです。
とくに「物質の変化」の分野は、よく出るパターンがある程度決まっており、解き方の“型”を身につければ得点源にしやすい単元でもあります。
「計算は苦手」と思っている人こそ、
学び方を少し変えるだけでグッと伸びる可能性がある分野なのです。
なぜ計算問題で手が止まってしまうのか?

理科の計算問題で手が止まる生徒の多くは、「計算ができない」のではなく、「どう考えていいのかわからない」という状態にあります。
その原因は、単なる計算力不足ではなく、情報の整理・理解・判断のプロセスにあります。
手順は知っていても、「なぜその手順なのか」がわからない
たとえば、質量保存の法則を使う問題で、
「反応前と後の質量が同じになるから、引き算すればいい」と覚えていても、
どの数字をどこに当てはめるかが曖昧だと、式を立てられません。
つまり、表面的な手順だけをなぞっても、“使いこなす”ことはできないのです。
単位・数値・式が「意味のあるもの」として見えていない
理科の計算では、単位(g、cm³、molなど)や数値の関係性を正しく理解していることが前提です。
しかし実際には、
- 「単位の変換を忘れる」
- 「比例関係を見抜けない」
- 「式の中の数字がどこから来たのか分からない」
といった混乱がよく見られます。これは、式や数値が“現象と結びついていない”ことが原因です。
問題文や表から「必要な情報を拾う」ことができていない
問題文に「水を加熱したときの質量変化について答えよ」と書かれていても、
- 表の中の“前後の質量”をどこから探せばいいのか
- どの数値を使って式を立てればよいのか
が分からず、最初の一歩が踏み出せない生徒が多くいます。
理科の計算問題は、「計算」自体よりも、
“どこに注目するか”“どんな式が必要か”という判断力が問われるのです。
このように、理科の計算問題で手が止まってしまう背景には、知識の未定着よりも「思考の組み立て方が分からない」ことによる不安や混乱があるのです。
つまずきを乗り越えるための具体的な対策
理科の計算問題は、ただ答えを覚えるだけでは解けるようになりません。
「なぜこの式になるのか」「どの数をどう使うのか」――
考え方の流れ=“解き方の型”を理解し、自分で再現できるようにすることがポイントです。
ここでは、苦手を克服するために今すぐできる具体的な学習法を4つ紹介します。
対策①:解説を写すだけでなく、「なぜその手順か」を考える
ノートに答えや式だけを写して「わかったつもり」になっていませんか?それでは、似た問題が出たときにまた手が止まります。
解くときは、頭の中でこう考えてみてください。
- 「なんでこの式なの?」
- 「この数字ってどこから出てきたの?」
- 「この単位(gやcm³)は、何を表してる?」
たとえば、
「反応前の質量が10g、反応後が8g。じゃあ発生した気体は2gだ」
このとき、“質量保存の法則”に気づいているかどうかが大事です。
意味を考えながら手を動かす。これが「理解する」ための第一歩です。
対策②:理解したら必ず“自力で解き直す”
「なるほど、そういうことか!」
そう思ったら、次にやるべきは「もう一回、自分の力でやってみる」ことです。
【ポイント】
・解き方を隠して、自分の手で解いてみる
・どこまで覚えていたか、どこで迷ったかを確認する
・間違えたら、「何を間違えたのか?」を自分で書き出してみる
たとえば前に解いた
「炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体の質量を求める問題」
があったとしたら、数日後にもう一度、何も見ずにやってみましょう。
本当に理解していれば、再現できるはずです。
対策③:類題で「考え方の型」を身につける
理科の計算問題には、「よく出るパターン」があります。
たとえば…
- 質量保存の法則を使う
- 水を温めたり冷やしたりすると質量が変化する
- 気体が発生したときに減った質量=気体の質量
【おすすめのやり方】
・1つの問題を解いたら、似た問題を2〜3問続けて解く
・同じ解き方が使えるとわかった瞬間、「おっ、分かってきたかも」と感じられる
・間違えたら、「なぜこのパターンに当てはめられなかったのか?」を振り返る
これを繰り返すことで、自然と“計算の型”が体に染み込んできます。
対策④:表・グラフは「目的を意識して読む」
問題に表やグラフがついていると、全部の数字を読みたくなってしまいがちです。
でも実は、大事なのは“問題で聞かれていること”だけに注目することです。
たとえば…
問題:「実験前と後で質量が変化している物質はどれか?」
このとき見るべきなのは、
- 実験前の質量
- 実験後の質量
- どの物質が減っている?増えている?
→ 表のその部分だけを探せばOK!
全部のデータを読み込もうとすると時間もかかり、迷ってしまいます。
「必要な情報をサッと見つけて使う」トレーニングが大事です。
この4つの対策をコツコツ実践していけば、
「なんとなくわかった」から「自分で解ける!」へ、確実にステップアップできます。
櫻學舎のサポート|「わかったつもり」で終わらせない指導

櫻學舎では、理科の計算問題に対して、「ただ答えが出ればOK」ではなく、「なぜそうなるのかまで理解できているか?」を重視した指導を行っています。
中学生がよくつまずく「物質の変化」単元の計算問題も、“手が止まる原因”を見つけ、そこに合わせた指導をすることで、一人ひとりの理解を深め、自信につなげています。
どこでつまずいたかを一緒に確認
まず大切にしているのは、「わからなかった原因」を一緒に見つけることです。
たとえば、
- 問題文の読み違い?
- 単位(g、cm³、molなど)の理解不足?
- 式の立て方がわからない?
- データの拾い方が不明確?
生徒によって原因はさまざまです。
櫻學舎では講師が生徒と一緒に「なぜできなかったのか」を分析し、次の一歩を明確にします。
「どうしてそうなるのか」を言葉で説明できるように
答えが合っていても、本当に理解できているかどうかは「説明できるか」で判断します。
たとえば、

講師:「この式って何を表してるの?」
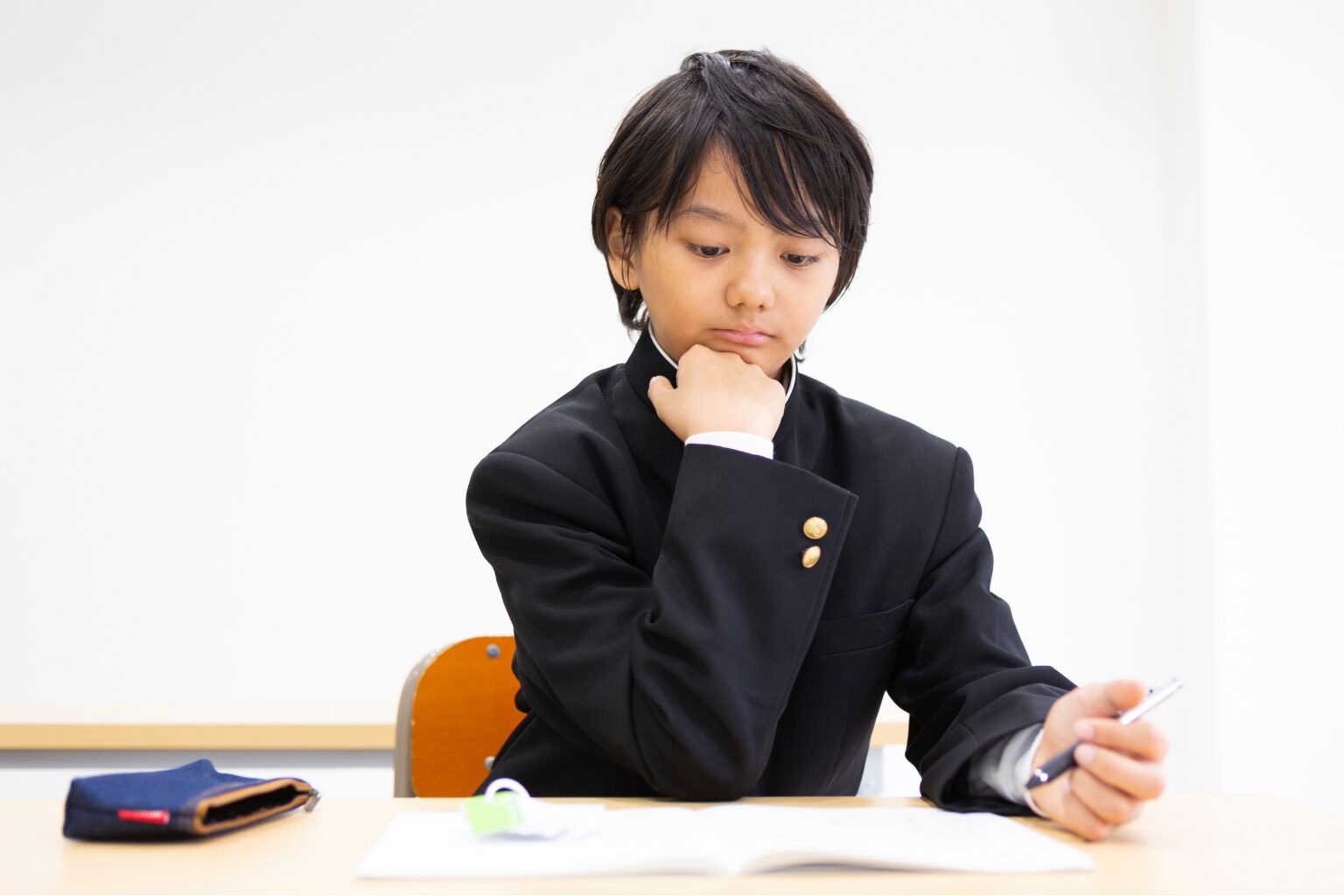
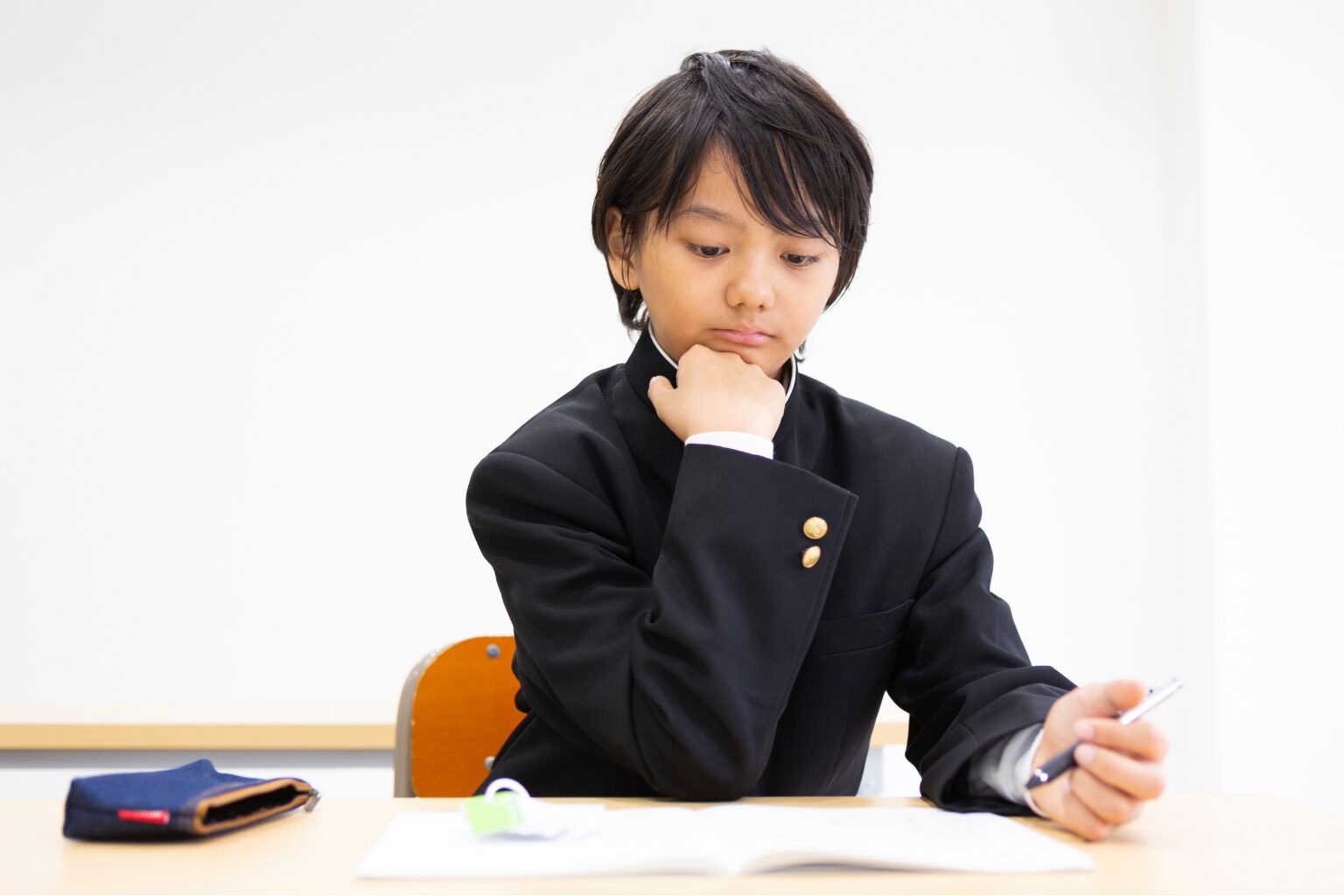
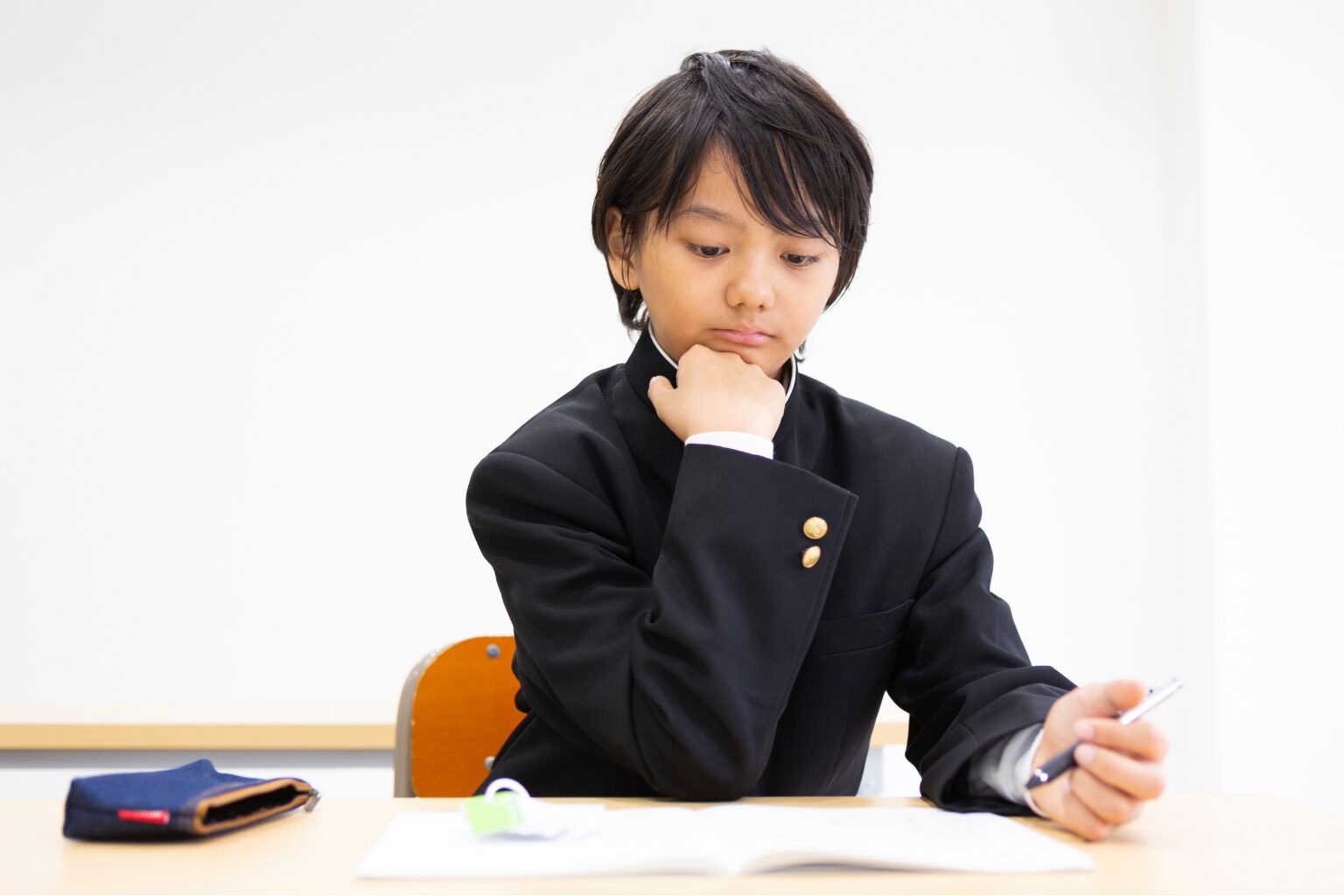
生徒:「…えっと、たしか…反応前の物質の重さを足したやつ?」
このやり取りを通じて、「なんとなく」から「自信を持って説明できる」状態を目指します。
説明できるということは、考え方が定着している証拠。
そこを目指して、講師が問いかけながら丁寧にサポートしています。
ノート指導で「思考の記録」を残す
ただ計算式を写すだけでは、あとから見返しても役に立ちません。
櫻學舎では、解いた内容と一緒に「気づき」や「ミスの原因」もノートに書くよう指導しています。
たとえば、
- 「単位の変換を忘れていた → 次はgとcm³をチェック」
- 「反応後の質量は気体の質量を引いたものになる」
- 「このパターンは何度も出てくる!覚える!」
こうすることで、ノートが“自分専用の参考書”になり、復習の効果が格段に上がります。
似た問題を繰り返し解いて「再現力」を育てる
最後は、「自分の力で解けるようになる」ことがゴールです。
そのために、理解した問題と似た問題をあえて連続で解いてもらうことで、
「考え方の型」をしっかり身につけてもらいます。
- 1回目:解き方を学ぶ
- 2回目:もう一度、自力で解く
- 3回目:似た問題で考え方が使えるか確認
このサイクルを通じて、「一問解けて終わり」ではなく、「応用できるところまで」到達する指導を徹底しています。
櫻學舎の理科指導は、「なんとなく分かった」を「自分でできる!」に変えるためのサポートにこだわっています。
計算問題を苦手なままにせず、成功体験を重ねて、自信を育てる。
そのための一人ひとりに合わせた学びの伴走が、ここにはあります。
まとめ:正しい手順と理解で、理科の計算は「できる」に変わる
理科の計算問題が苦手…そんな悩みを抱えている中学生は少なくありません。
特に「物質の変化」単元では、ただ公式を覚えるだけでは通用せず、手順の意味、数値や単位の関係性、そして情報の読み取り力が問われます。
しかし、苦手の正体は「センスがない」ことではありません。
ほとんどの場合、手順と意味のつながりが曖昧なまま暗記だけで進んでしまった結果なのです。
この記事でご紹介したように、
- 「なぜその式なのか」を考えて解く
- 自力で解き直して理解を確かめる
- 類題を通して考え方のパターンを体で覚える
- 表やグラフは“問いに応じて読む”習慣をつける
といった学習の工夫を積み重ねていけば、理科の計算問題は必ず克服できます。
櫻學舎では、一人ひとりの「つまずきの原因」に寄り添いながら、“解けるようになる”までのプロセスをしっかりサポートしています。
「理科はちょっと苦手かも…」と感じている今こそ、変われるチャンスです。
正しい学び方で、一歩ずつ「できる自分」を育てていきましょう。








