古文敬語を完全攻略!「誰→誰に」を見抜けば主語も人間関係もスラスラ読める
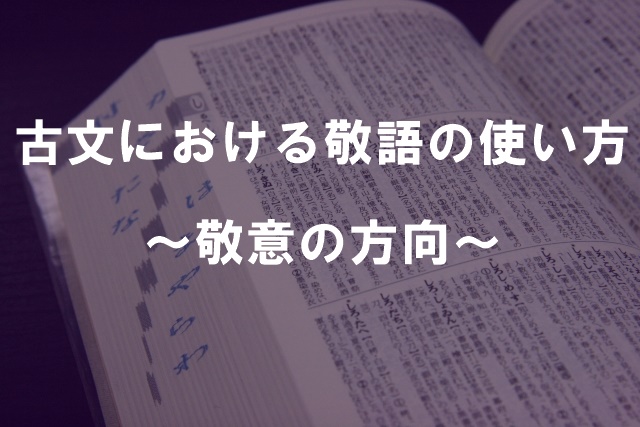
こんにちは、櫻學舎の早坂です。
古文の読解で必ずといっていいほど出てくるのが「敬語表現」です。
尊敬語・謙譲語・丁寧語といった分類は知っていても、
「この敬語は誰に向けられているのか?」
「地の文と会話文では意味が変わるの?」
と悩んだ経験はありませんか?
実は、敬語を正しく読み取れるかどうかで、古文読解の理解度は大きく変わります。
主語や人間関係を正しく把握できるようになれば、文章全体の流れがクリアになり、得点力もグッと上がるのです。
この記事では、古文敬語の基本である 尊敬語・謙譲語・丁寧語の違い から、入試でよく出題される 二方向敬語・絶対敬語・自敬表現 までを詳しく解説します。
「誰が→誰に敬意を向けているのか」を見抜くコツを身につけて、敬語問題を得点源にしていきましょう。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑
\ 無料学習カウンセリング実施中 /
古文の敬語とは?|尊敬語・謙譲語・丁寧語の違い
古文における敬語表現は、単に「丁寧な言い方」ではありません。
話し手が誰に対して敬意を表しているのかを読み取ることで、主語の特定や人物関係の理解に大きく役立ちます。
特に入試では、「誰が」「誰に」対して使った敬語なのかを見抜くことが、読解問題のカギとなります。
古文の敬語は大きく分けて、尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類があります。
それぞれの役割と使い方を整理してみましょう。
尊敬語|動作主を高める敬語
尊敬語は、動作をする人(=主語)を高めるための表現です。
相手や身分の高い人の行動を敬って述べるときに使われます。
現代語訳では「お〜になる」「〜なさる」といった形になります。
たとえば、「給ふ(たまふ)」や「おはす」などが尊敬語にあたります。
例文:「牛若丸、笛吹き給ふ」
→ これは筆者が牛若丸の動作を尊敬して述べている表現です(=“牛若丸が笛をお吹きになる”)。
謙譲語|動作の相手を高める敬語
謙譲語は、自分(または自分側の人物)をへりくだらせて、動作の相手を高める表現です。
相手に対して敬意を示すために、自分の行動を控えめに述べます。
現代語訳では「〜申し上げる」「〜いたす」などになります。
たとえば、「奉る(たてまつる)」「参る(まゐる)」などが謙譲語です。
例文:「若君、姫君に文書き奉る」
→ 若君が自分の行動をへりくだって、姫君に敬意を表していると読み取れます。
丁寧語|聞き手に対して丁寧に述べる敬語
丁寧語は、話し手が聞き手に対して丁寧に述べるときに使われます。
現代語の「〜です」「〜ます」に近い働きを持ちます。
代表的な表現に「侍り(はべり)」「候ふ(さぶらふ)」などがあります。
例文:「うれしと思ひ侍り」
→ “うれしく思います”と、読み手や聞き手に対して丁寧な語り口で述べていると解釈できます。
3つの敬語の違いをまとめると…
| 敬語の種類 | 敬意を向ける相手 | 主な訳し方 | 例 |
|---|---|---|---|
| 尊敬語 | 主語 | お〜になる、〜なさる | 給ふ、おはす |
| 謙譲語 | 動作の相手 | 〜申し上げる、〜いたす | 奉る、参る |
| 丁寧語 | 聞き手・読み手 | 〜です、〜ます | 侍り、候ふ |
まずはこの3つの基本的な敬語の性質と、誰に敬意を向けているかという「敬意の方向」をしっかり押さえておきましょう。
この土台があれば、地の文・会話文に出てくる複雑な敬語の読み取りも格段にスムーズになります。
地の文と会話文で異なる!敬語の「方向性」
古文の敬語を正しく読み取るためには、「誰が誰に敬意を示しているか」という敬意の向き(=方向性)を見抜くことが最も大切です。
ここでポイントになるのが、その敬語が使われているのが「地の文」なのか「会話文」なのかという点です。
同じ単語でも、地の文と会話文では、敬意を向ける相手がまったく違うことがあります。
地の文の敬語|筆者(=作者)からの敬意
地の文とは、物語の中で語り手(=筆者・作者)が状況や登場人物の動作を説明している部分のことです。
この場合、敬語は「筆者が登場人物をどう見ているか」を表します。
つまり、筆者がその人物を敬っているかどうかが敬語の使われ方にあらわれるのです。
例文:「牛若丸、笛吹き給ふ」
→ 尊敬語「給ふ」が使われているので、筆者は牛若丸を敬っていると分かります。
このとき、牛若丸が「身分の高い人物」や「重要な人物」である可能性が高いことが読み取れます。
例文:「若君、姫君に文書き奉る」
→ 謙譲語「奉る」は、若君が姫君に敬意を表していると筆者が描写している文です。
会話文の敬語|話し手からの敬意
一方で、会話文に出てくる敬語は、物語中の登場人物どうしのやり取りで使われる敬語です。
この場合、敬語が示すのは「話し手が誰に敬意を表しているか」です。
つまり、登場人物間の人間関係を敬語から読み取ることが求められます。
例文(地の文):「女房が中宮にそのことを申す」
→ 謙譲語「申す」=女房 → 中宮への敬意。筆者が女房の立場から中宮を敬って描写している。
これが会話文になると…
「御使が『女房が中宮にそのことを申す』と言ふ」
→ このとき敬語「申す」は、話し手である御使が、中宮に対して敬意を示していることになる。
つまり、同じ文言でも、誰の視点かによって敬語の向きが変わるというわけです。
地の文と会話文の違いを意識しよう
| 文の種類 | 敬語の方向性 |
|---|---|
| 地の文 | 筆者(作者)→ 登場人物 |
| 会話文 | 話し手(登場人物)→ 会話の相手 |
この違いを意識して読めるようになると、
「この人物は尊敬されている」「この人物は身分が高い」「この人に対して謙譲語を使っている」など、
登場人物の人間関係や物語の構図が一気に読みやすくなります。
次の章では、さらに一歩進んで「尊敬語と謙譲語が同時に使われる」パターン=二方向敬語を見ていきましょう。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑
\ 無料学習カウンセリング実施中 /
尊敬語+謙譲語の「二方向敬語」
古文の敬語表現には、尊敬語と謙譲語が同時に登場する文があります。
これは「二方向敬語」と呼ばれ、一つの文の中で、主語と目的語の両方に敬意を示す表現です。
このパターンを読み取れるかどうかで、
- 主語の特定
- 敬意の向き
- 登場人物の身分関係
などの理解度に大きな差が出てきます。
例文①:「御文奉りたまふ」
この文には、
- 「奉る」… 謙譲語(相手を高める)
- 「たまふ」… 尊敬語(主語を高める)
が同時に使われています。
それぞれの方向を整理すると、
- 「奉る」…謙譲語
→手紙を受け取る相手(天皇など) へ敬意 - 給ふ…尊敬語
→手紙を書いている主語(かぐや姫など) への敬意
つまり、「御文奉りたまふ」は、かぐや姫が天皇に手紙を差し上げる(=主語・相手の両方を敬っている)という構図になります。
例文②:「見たてまつりたまはむや」
この文にも2つの敬語が入っています。
- 「たてまつる」… 謙譲語(見る対象への敬意)
- 「たまふ」… 尊敬語(見る動作をする人への敬意)
この場合は、尼君(主語)が、光源氏(対象)に対して敬意を込めて「お見申し上げる」と言っている文脈です。
どちらも高貴な人物であるため、両方に敬意が払われているわけです。
二方向敬語の読み方のコツ
- 文中に敬語が2つあるかをチェック
- それぞれの敬語が 誰に向かっているか(主語 or 目的語) を判断
- 登場人物の身分や関係性と照らし合わせて主語・構造を読み解く
この敬語の読み方は、入試の記述問題や選択問題で特に差がつくポイントです。
一見するとややこしく見えますが、「主語を尊敬しているのか」「相手を謙譲しているのか」 を一つ一つ見分ければ大丈夫です。
次の章では、さらに特別な敬語表現である「二重敬語」「絶対敬語」「自敬表現」について詳しく見ていきます。
二重敬語・絶対敬語・自敬表現
古文には、尊敬語・謙譲語・丁寧語の基本に加えて、特別な使い方や決まったルールを持つ敬語表現がいくつか存在します。
ここでは、入試にもよく出題される 「二重敬語」「絶対敬語」「自敬表現」 の3つについて解説します。
二重敬語(最高敬語)
二重敬語とは、同じ主語に対して複数の尊敬語を重ねて使う表現のことです。
非常に高い敬意を込めており、皇族や貴族など、極めて身分の高い人物に対して使われます。
例文
「殿、見させ給ふ」
→ 「見させ」も「給ふ」も尊敬語で、動作主である「殿」に対して重ねて敬意を示しています。
「帝、歩ませ給ふ」
→ 「歩ませ」は尊敬の補助動詞、「給ふ」は尊敬語。帝(天皇)に対して最高の敬意を表す。
ポイント
- 主語が高貴な人物である
- 一つの動作に対して二重に尊敬語を使っている
- 「最高敬語」として出題されることがある
絶対敬語(使用対象が限定される)
絶対敬語とは、使用できる対象が厳密に決まっている敬語のことです。
これらは天皇や皇族など、特定の身分の人にしか使いません。
| 敬語 | 意味 | 使用対象 |
|---|---|---|
| 奏す(そうす) | 申し上げる | 天皇・上皇 |
| 啓す(けいす) | 申し上げる | 皇后・中宮・皇太子 |
例文
「中将、その旨を奏す」
→ 中将が天皇に申し上げる。
「女御、帝の御心を啓す」
→ 女御が中宮に申し上げる。
ポイント
- 動詞そのものが敬意の方向を決定している
- 相手が誰かを判断するヒントになる
- 「誰に対して使われているか」を明確に判断する必要がある
自敬表現(自分で自分を敬う)
自敬表現とは、高貴な人物が、自分自身の行動に対して敬語を用いる表現です。
現代語ではあまり見られない独特な使い方ですが、古文では天皇や貴人が自分を高めるときに使います。
例文
「君、参れと仰せければ」
→ 「参れ」は本来、謙譲語で相手の動作をへりくだって表すが、ここでは 君(=高貴な主語)が自分自身に対して 使っている。
ポイント
- 高位の人物が自分に対して敬語を使う
- 一般人では使用しない
- 「おかしいな」と思っても、身分を考慮すれば自然な表現になる
敬語タイプの整理表
| 表現の種類 | 特徴・意味 | 使用対象・注意点 |
|---|---|---|
| 二重敬語 | 同じ主語に2つの尊敬語 | 高貴な人物に対しての最高敬意 |
| 絶対敬語 | 使用対象が限定される敬語 | 奏す=天皇、啓す=皇后・中宮・皇太子 |
| 自敬表現 | 高貴な人物が自分に使う敬語 | 一般人が使うと不自然、文脈で見抜く必要あり |
このように、基本の敬語とは少し異なる「特別な敬語表現」も知っておくことで、文章の意味をより深く正確に読み取れるようになります。
次の章では、ここまで学んだことを活かして「敬語の読み方の実践ポイント」を紹介します。
古文敬語対策のカギ|「誰→誰に」を見極める
古文の敬語を正しく読み解くために最も重要なのは、「誰が→誰に」敬意を向けているのかを見極める力です。
敬語の種類(尊敬語・謙譲語・丁寧語)が分かっていても、その敬語が「誰の立場から」「誰に向けて」使われているかを読み間違えると、登場人物の人間関係や主語の特定に大きなズレが生じてしまいます。
この「敬意の向き」を読み取るには、次の2つの視点がカギになります。
1つ目の視点:地の文か会話文かを見分ける
古文では、地の文(筆者による叙述)と会話文(登場人物の発言)で、敬語の方向性が変わります。
- 地の文:筆者が登場人物に敬意を表している
- 会話文:その発言をしている登場人物(話し手)が、相手に敬意を表している
この違いを見分けることで、誰の視点で敬語が使われているのかを把握することができます。
2つ目の視点:敬語の種類から主語と目的語を推定する
敬語の種類ごとに、敬意を向ける対象が異なります。
そのため、どの敬語が使われているかによって、「誰が動作主で、誰が対象か」が見えてきます。
- 尊敬語:動作主(=主語)を高める
→ 敬語が使われている動詞の主語は、身分の高い人物や、敬意を受ける立場の人物 - 謙譲語:動作の相手(=目的語)を高める
→ 主語は下位の立場で、対象は上位者や中心人物 - 丁寧語:聞き手や読み手を高める
→ 地の文では作者→読者、会話文では話し手→聞き手に敬意
この2つの視点を同時に意識して読み進めることで、
「この敬語は誰の発言で、誰に向けた敬意なのか?」
「主語は誰で、目的語は誰なのか?」
といった文の構造が自然と見えるようになります。
たとえば、「奉る」などの謙譲語が使われていれば、その動作の相手が重要人物であると分かり、
「給ふ」などの尊敬語が使われていれば、主語の人物が高貴である可能性が高いと推測できます。
実際の読み取りの例
例1:「若君、姫君に文書き奉る」
→ 地の文。謙譲語「奉る」が使われている。
→ 若君(主語) → 姫君(対象)に敬意
→ 姫君が上の立場であると読み取れる
例2:「御使が『女房が中宮にそのことを申す』と言ふ」
→ 会話文。「申す」は謙譲語。話者は御使。
→ 女房→中宮という動作を、御使の視点で敬意を示している
→ 中宮が敬意の対象=高位
見極めのコツ
- 敬語が「誰の行動」について語っているかを見る(動詞の主語)
- その敬語が「誰に向けられているか(対象)」を特定する
- 地の文なら筆者、会話文なら話し手の視点で敬意の向きを判断する
方向性の意識が入試で差をつける!
入試の読解問題では、主語の推定や人間関係の把握を問う問題が頻出です。
敬語の方向性を見誤ると、人物関係が逆転してしまい、記述問題や選択問題での正答率が大きく下がってしまいます。
だからこそ、常に「この敬語は、誰が、誰に向けて使っているのか?」を意識する習慣を身につけましょう。
まとめ
古文の敬語は、一見すると複雑に見えますが、基本を押さえて丁寧に読み解けば、必ず得点源になります。
重要なのは、敬語の種類そのものよりも、誰が→誰に対して敬意を示しているかという「敬意の方向性」を見極めることです。
尊敬語は主語を、謙譲語は目的語(動作の相手)を、丁寧語は聞き手を高めるという基本原則をもとに、
文が地の文なのか会話文なのか、登場人物の関係性はどうなっているのかを読み取る力を養っていきましょう。
また、敬語表現を通じて主語や視点を正確にとらえる力は、現代文の読解や記述力の強化にもつながります。
文章の構造を意識する訓練としても、古文敬語の学習は非常に有効です。
今回学んだ知識を、演習や過去問で実際に使ってみることで、「読み取れる実感」と「解ける手応え」がどんどん積み重なっていきます。
ぜひ繰り返し復習しながら、自分の武器にしていきましょう。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑
\ 無料学習カウンセリング実施中 /








