【第2回】英文和訳の極意|thatの正体を見抜け!接続詞・関係詞の見分け方と和訳テクニック
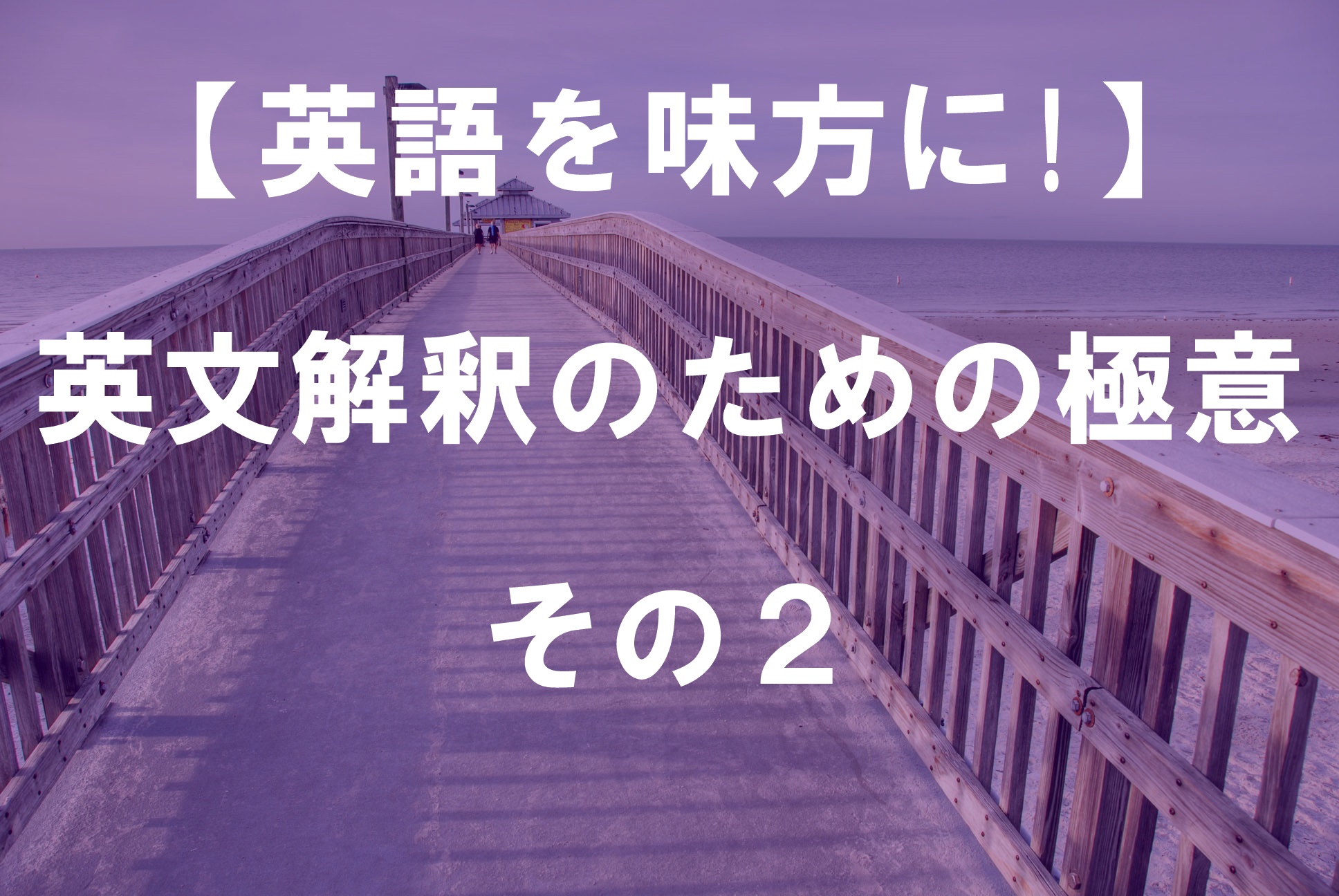
受験生の皆さんこんにちは。
私のブログでは今回から数回にわたって英文和訳の方法について書いていきます。
この「英文解釈の極意」をしっかり読んで英語を得点源にしていきましょう。
前回は英文を訳す上での枠の作り方を学習しました。
今回も英文解釈の極意をいくつか紹介していきます。
まずは例文を見てみよう
まずは問題を見てみましょう。
下の英文を和訳しなさい。
This is the coldest winter that we have had in twenty years.
難しい文章ではないですが、順を追ってしっかり読み解いていきましょう。
まずは、前回同様動詞(V)を見つけます(極意その1)。
今回は is と have ですね。
しかし、ここで問題が生じます。
英文には動詞が一つと決まっています。
ひとつといっても文章のメイン(主節)になる動詞がひとつなわけで、ほかの動詞が動詞じゃなくなるわけじゃありません。
では、どうやって主節のVを見つけられるのでしょうか。
ここで今回の極意が出てきます。
極意6:V の数と接続詞/関係詞の数
This【is】the coldest winter that we have【had】in twenty years.
今回の英文にはVが2個(is、have)存在します。
ということは、この英文中には1個の接続詞、ないし関係詞が存在することになります。
この英文ではthatがその役割を果たすことになるのは予想がつきますね。
では、このthatは接続詞でしょうか?関係詞でしょうか?
ちなみにthatは接続詞にも関係詞にもなるのです。
したがって、今回はthatの見極めが必要なのです。
そこで次の極意です。
極意7:接続詞か関係詞か?
This【is】the coldest winte [that] we have【had】in twenty years.
現在のところ分かっているのはVが2個、thatが接続詞か関係詞かということです。
接続詞と関係詞の見分け方は以下の点に注意しさえすれば問題ありません。
thatの後ろの文が成立している場合→接続詞
thatの後ろの文が不成立の場合→関係詞
成立しているというのは文章として必要な要素(SVときにはOC)がそろっていることで、不成立の文章はその必要な要素が抜けていることを指します。
今回の場合that以下の文はwe have had in twenty yearsでhadの後ろに具体的な名詞がないので不成立の文となります。
したがって今回のthatは関係詞となり直前の名詞を説明する役割を担うのです。
このとき接続詞や関係詞が前に来るVは文の主節にはならないということも覚えておいてください。
さあ、文の要素が固まってきたところでいよいよ訳していきましょう。
実際に訳してみよう
This is the coldest winter that we have had in twenty years.
さあ、文の要素が固まってまいりましたので実際にこれまでの極意にしたがって訳していきましょう。
まずは主節となるVをとらえます(極意1)。
今回thatが関係詞(極意6,7)からhaveは主節のVにはならないため、今回の主節のVはisとなります。
ここからVを中心に和訳のための枠を設定していきます(極意2)。
This is the coldest winter ~
be動詞はS=Cとする(極意4)ことから
これはもっとも(that以下の)寒い冬だ。
という枠が出来上がります。
あとはthat以下を訳すだけなのですが、ここにも極意があります。
極意その8 関係詞や接続詞を含む文もVは1個
接続詞や関係詞で囲まれた文章でも英語のきまりは一緒です。
したがって接続詞や関係詞は直後のVの次のVがあった場合はその2個目のVの直前まで文の要素として考えることになります。
今回はthat以下の文章は
「we have had in twenty years.」
that以下に2個目の動詞はないのでthatはthat以下すべての文章を含むと考えられます。
したがって、ここでも極意にしたがって文頭から訳していくと、
「私たちがこの20年間に持った」
という訳になります。
haveは所有する意味合いの非常に用途が広い単語ですので、今回は季節のことを前文で言っているので「経験した」くらいにしておくのがよいでしょう。
that以下も訳せたところで、二つの文章を組み合わせると
今年はこれまでの20年間で経験したなかでもっとも寒い冬だ。
という訳が完成します。
以上のことから、以下のように訳すことができます。
This is the coldest winter that we have had in twenty years.
今年はこれまの20年間で経験した中でもっとも寒い冬だ。
よくあるミスと注意点
英文解釈の習得には「型」や「ルール」の理解が欠かせません。とはいえ、初学者にとっては見落としやすいポイントも多く、ありがちな誤解やミスが発生しやすいのも事実です。
ここでは、今回のテーマに関して特に注意しておきたい点をまとめました。
ミス①:「that」をすぐに接続詞と決めつけてしまう
どうしてミスになる?
英語学習で初期に「thatは接続詞=〜ということ」と教わることが多いため、つい「that=接続詞」と短絡的に判断しがちです。
正しい見分け方
- 文として成立していれば → 接続詞
- 要素が欠けていれば → 関係詞(that以下は名詞を修飾)
【例】
× This is the coldest winter that we have had → 接続詞と誤認
〇 このthatは 「winter」を修飾する関係詞(目的語が省略されている)
ミス②:動詞(V)をすべて見つけられていない
どうしてミスになる?
英語の文章は一見短くても、完了形・受動態・助動詞とのセットなどで複数のVが入り組んでいます。
見た目に惑わされて「動詞は1個だけだろう」と早とちりしてしまうことがあります。
正しい見方
完了形や助動詞もVとみなされるので要注意です。
【例】
we have had in twenty years
→ これは 完了形(have + 過去分詞)なので、動詞として1セットでカウント!
ミス③:「主節」と「従属節」をごちゃまぜにしてしまう
どうしてミスになる?
文の要素を見つけても、それがどの文(主節or関係詞節)に属しているかを見分けないと、訳の順番が狂ったり、意味が崩れたりしてしまいます。
正しい対処法
主節が見えれば、「どこに肉付けされている情報なのか」が明確になります。
ミス④:「have」の意味を機械的に「持っている」と訳す
どうしてミスになる?
「have=持っている」という訳に引っ張られると、今回のような「経験を表す完了形」が不自然な訳になります。
正しい理解
文脈に応じて、「〜したことがある」「〜してきた」「〜し終えた」など柔軟に解釈するのが重要です。
【例】
we have had this winter
→ 「この冬を持っていた」ではなく、「この冬を経験した」とするのが自然!
まとめ
ここで今回の極意のまとめです。
- 極意6 Vが一文に複数ある時はVの数より1少ない数だけ接続詞、もしくは関係詞が存在する
- 極意7 接続詞と関係詞の見極めは後ろの文の成立をみよ。
- 極意8 関係詞や接続詞を含む文もVは1個
以上です。今回は文章を分ける接続詞と関係詞を中心にやりました。
次回以降もより良い英文和訳のための極意を伝授していきます。
お楽しみに~。








