入試英語で差がつく!英文解釈の実践トレーニング|新潟大学の過去問で学ぶ構造分析のコツ
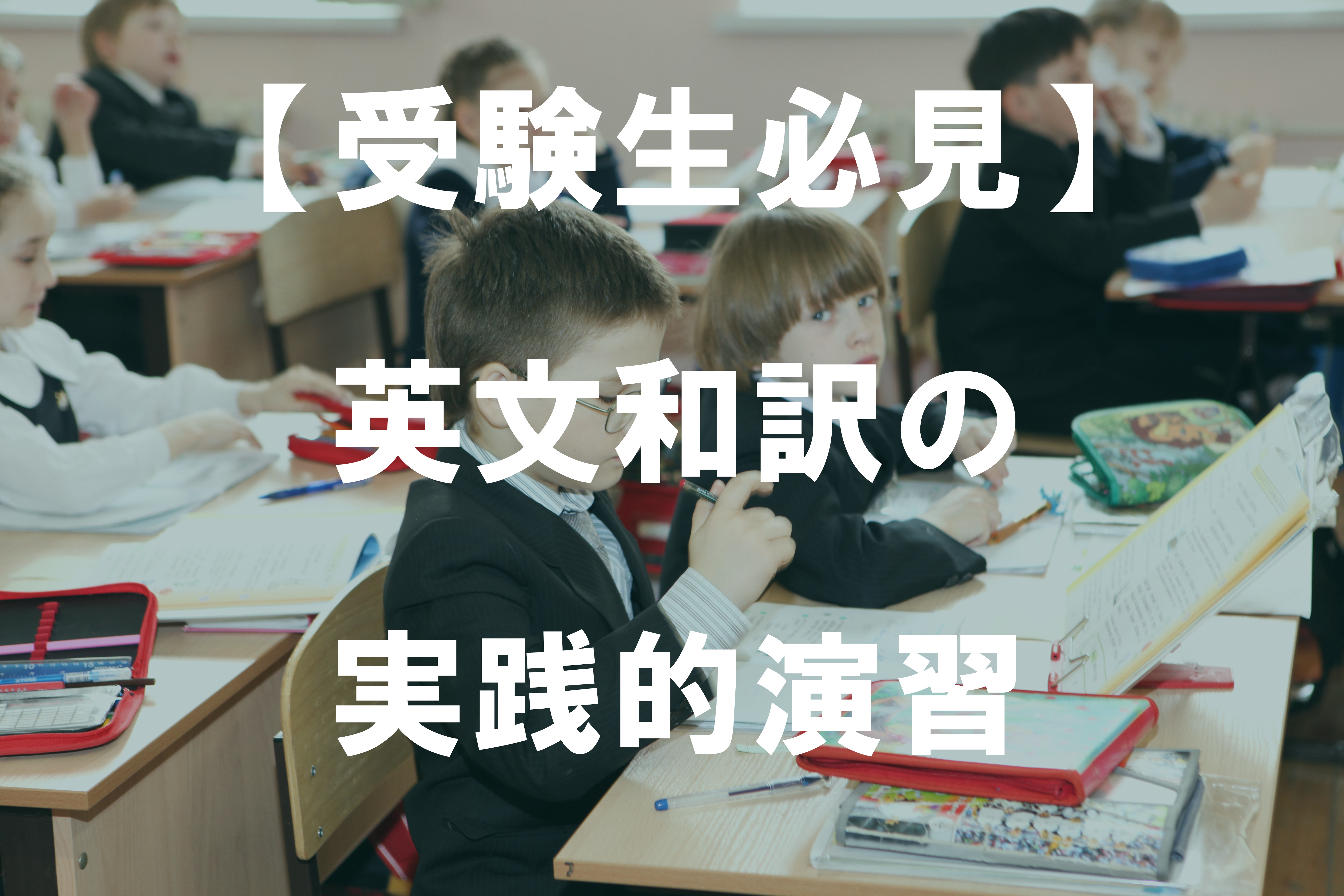
大学入試の英語長文や和訳問題では、一見すると複雑で長い英文が出題されることがあります。
しかし、実際に点数を取るために必要なのは、すべてを完璧に訳す力ではありません。
重要なのは、「文の骨組み=構造を見抜く力」と「よく使われる表現を知っているかどうか」。
今回は、新潟大学の入試で実際に出題された英文を取り上げ、どのように構造を把握し、どう訳していけばよいのかをステップごとに解説します。
「接続詞の働き」や「イディオムの見抜き方」など、実践的なコツも紹介していきますので、英語が苦手な方もぜひチャレンジしてみてください!
最後には、「入試英文を読むための力をどう身につけていくか」もお伝えします。
それでは一緒に、英文の奥深さと面白さを体感していきましょう!
演習問題
それでは、実際に出題された英文を使って演習を行ってみましょう。
今回は 新潟大学 の入試問題から抜粋した、やや長めの英文です。
問題:次の英文を和訳しなさい。
He can hear members of the family coming home before we can hear them and he can tell one person’s footstep from another’s.
この英文のポイントは、一見シンプルな語で構成されていながら、構造が少し複雑に感じられる点です。
また、並列の構造(and)やイディオム(tell A from B)が含まれており、英語の「骨組み」を意識して読む力が試される内容となっています。
次の章では、構造の把握と意味の理解のための ステップ別の解説 を行っていきます。
Step 1|英文の大枠をつかむ
英文を正確に訳すための第一歩は、「一文全体の大枠をとらえること」です。細かい文法や単語の意味をいきなり追うのではなく、まずは構造を見渡して、どこが主語・動詞なのか、どこで文が区切られているのかを把握することが大切です。
He can hear members of the family coming home before we can hear them and he can tell one person’s footstep from another’s.
この文は次のように大きく2つのパートに分けることができます。
文の2つの柱を見抜こう
英文の中にある 「and」 が、2つの主節(独立した意味を持つ文)をつないでいるのがわかります。
- He can hear ~(彼は~を聞き取れる)
- He can tell ~(彼は~を区別できる)
つまり、主語(He)と助動詞+動詞(can hear / can tell)のセットが2つあり、それがandでつながれています。これが 英文の大枠 です。
ポイントは「並列構造」
英文の読み方でよく使われるのが、この「並列構造」の見抜き方です。
接続詞 and や but などがある場合、それが どの文要素をつないでいるか をチェックすると、長文でも構造が見えやすくなります。
今回は、
- He can hear … and he can tell …
というように、「主語+動詞」が2つ並んでいる=2つの主節が並列しているという構造です。
大枠がつかめれば、訳す準備が整う!
長文や複雑な英文を訳す際に、いきなり単語から訳そうとすると、意味がバラバラになってしまいがちです。しかし、今回のように「主語と動詞のセット」を見つけることで、文全体の構造が見え、迷わず訳しやすくなります。
次のステップでは、それぞれの文の中身を分解し、文法要素や語句の働きを詳しく見ていきます。
Step 2|前半部分の解釈(before節を含む)
英文の大枠をつかんだあとは、それぞれの節の中身を丁寧に読み解いていきましょう。今回はまず、文の前半部分を詳しく分析します。
取り上げる部分は以下です。
He can hear members of the family coming home before we can hear them
主語と動詞の確認から始めよう
まずは文の骨組みとなる 主語(S)と動詞(V) を明確にします。
- 主語(S):He(彼/犬)
- 助動詞+動詞(V):can hear(聞くことができる)
この時点で、「彼は~を聞くことができる」という文の主幹がつかめます。
目的語と修飾語を分解する
次に、「何を聞くのか」を見ていきましょう。
- members of the family coming home
→ 「帰宅する家族のメンバーたち」
ここで注意したいのは、coming homeがmembersを修飾しているということです。つまり、「帰宅する」のは家族そのものではなく、その中のメンバーです。
接続詞「before」が意味すること
文の後半には、接続詞 before が登場します。
before we can hear them
→ 「私たちが彼らのことを聞くことができる前に」
これは、時間的な先行関係を表しています。
つまり、
- 「犬は(He)、人間(we)よりも先に、帰宅する家族の音を聞き取ることができる」
という意味になります。
ここまでの訳文(前半)
He can hear members of the family coming home before we can hear them
→「彼(犬)は、私たちがそれに気づくよりも前に、帰宅する家族の足音を聞き取ることができる」
このように、主語と動詞をつかみ、目的語・修飾語・接続詞の働きを順に整理していくことで、自然で的確な訳が完成します。
次のステップでは、「and」以降の後半部分を分析していきましょう。
Step 3|後半部分の解釈(イディオムを見抜く)
前半部分で主節の構造を確認し、「犬は人間より早く家族の帰宅に気づく」ことを理解しました。ここからは、and 以下の後半部分を見ていきましょう。
and he can tell one person’s footstep from another’s.
まずは構文を整理する
ここも主語と動詞を確認するところから始めます。
- 主語(S):he(彼/犬)
- 助動詞+動詞(V):can tell(見分けられる)
これで、「犬は〜を見分けることができる」という構造が見えてきます。
イディオムの見抜きがカギ!
この文の核となるのは、tell A from B という表現です。
この表現は 「AとBを区別する、見分ける」 という意味のイディオムです。受験英語では頻出の重要表現なので、しっかり覚えておきましょう。
- tell one person’s footstep from another’s
→ 「ある人の足音と、別の人の足音を区別する」
ここでは「one person」と「another person」(もう一人の人)という2人を対比しており、それぞれの足音の違いを聞き分けているという文脈です。
所有格の省略にも注意!
最後の another’s は another’s footstep の省略形です。
文の流れをつかめていないと、「なんで’sだけで終わってるの?」と戸惑うかもしれませんが、これは文法的にごく自然な省略です。同じ名詞が繰り返されるとき、後半は’sだけで済ませるのが英語の習慣です。
ここまでの訳文(後半)
and he can tell one person’s footstep from another’s.
→「そして彼(犬)は、ある家族の足音と、別の家族の足音とを聞き分けることができる。」
Step 4|全体の和訳を完成させる
ここまでのステップで、英文の構造、意味のかたまり、そして重要表現をひとつずつ分解して理解してきました。
最後に、それらをつなぎ合わせて自然な日本語の訳文に仕上げていきましょう。
元の英文を再確認
He can hear members of the family coming home before we can hear them, and he can tell one person’s footstep from another’s.
ポイントを整理
- 主節①:He can hear members of the family coming home
→ 「彼(犬)は家族のメンバーが帰ってくるのを聞くことができる」 - 従属節:before we can hear them
→ 「私たちがそれを聞く前に」 - 主節②:and he can tell one person’s footstep from another’s
→ 「そして彼は、ある人の足音を別の人のそれと聞き分けることができる」
直訳から自然な訳へ
これらの要素をそのままつなぐと、以下のような直訳調になります。
彼は、私たちが聞くよりも前に、家族の誰かが帰ってくるのを聞くことができ、また、ある人の足音を他の人のそれと聞き分けることができる。
このままでも意味は伝わりますが、より自然な日本語に仕上げるには、語順や言い回しを少し調整します。
自然な日本語訳(完成版)
犬は、私たちよりも早く家族の帰宅に気づき、さらに、家族一人ひとりの足音を聞き分けることができる。
翻訳の完成度を上げるポイント
- 「聞く」→「気づく」:英語では “hear” でも、日本語では状況に応じてより適切な動詞に置き換える。
- 「one person’s footstep from another’s」→「家族一人ひとりの足音」:逐語訳ではなく、意図をくみ取った意訳にすることで読みやすくなる。
- 全体を一文でつなげる:日本語では短く滑らかな一文にまとめる方が自然。
英文解釈は単語力や文法知識だけでなく、「どんな場面を描いているか」という状況把握力も大切です。
今回の問題では、接続詞の働きやイディオム表現、語順の整理を意識することで、しっかりとした訳文にたどり着くことができました。
まとめ|英文解釈のコツと今回のポイント
英文解釈は、一見すると複雑で難解に思えるかもしれません。
しかし、今回のように 文の構造をつかむ → 意味のまとまりを見抜く → イディオムや文法知識を活用する → 自然な訳に仕上げる というステップを踏めば、確実に読めるようになっていきます。
今回のポイントを振り返ると、
- 接続詞の役割を見抜いて、文の骨格を整理する
- イディオム表現を知識として押さえておく
- 訳す際は前から順に処理しながら、日本語として自然に仕上げる
といった基本が非常に重要でした。
英語の長文問題も、焦らず「まず構造を見てから中身を読んでいく」姿勢を持てば、難問にも冷静に立ち向かえるようになります。
引き続き、演習を通じて読解力と訳す力を鍛えていきましょう!
学習アドバイス|英文解釈力を伸ばすには
英文解釈の力は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、正しい方法で継続して取り組めば、確実に力は伸びていきます。ここでは、英文解釈力を伸ばすための具体的な学習アドバイスをお伝えします。
①「構造」を意識する癖をつける
英文を読むとき、「主語・動詞はどこか?」「この節はどの文にかかっているのか?」といった構造面に注目しましょう。単語の意味を追うだけでなく、文全体の骨組みを把握する意識が大切です。
② 知識を「活用できるレベル」に引き上げる
文法やイディオムの知識は、知っているだけでは不十分です。実際の英文に出てきたときに、それを即座に見抜いて使いこなせるようにするには、反復演習とアウトプットが欠かせません。問題演習や音読で、知識を“使う力”へと変えていきましょう。
③ 和訳練習は「自然な日本語」を目指す
訳を作るときは、直訳にこだわりすぎず、伝わる日本語になるように調整する力も必要です。文構造を正確に押さえたうえで、読み手にとって自然でわかりやすい日本語に仕上げることを意識して練習しましょう。
④「自分で解説できるか?」を基準に復習
英文解釈の復習で最も効果的なのは、「この英文を人に説明できるか?」という視点です。もし説明できない部分があるなら、そこに理解の穴がある証拠です。自分の言葉で説明する習慣を持つことで、より深い理解につながります。








