「囲碁と将棋」で学力アップ?右脳と左脳を鍛える最強の古典ゲーム
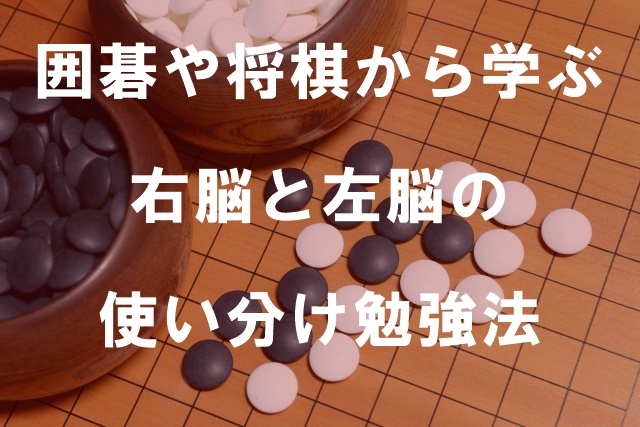
こんにちは、櫻學舎です。
最近はスマホゲームがたくさん登場し、「勉強の邪魔」とされることも多いですが、皆さんは「囲碁」や「将棋」といった、日本古来の盤上ゲームに注目したことはありますか?
「なんだか古臭そう……」と思う方もいるかもしれません。
でも実はこの囲碁や将棋、ゲームとしての魅力だけでなく、「思考力」や「集中力」「先を読む力」を鍛える、非常に優れた学習ツールなんです。
今回は、囲碁と将棋が学習にどう役立つのか、塾としての視点からご紹介していきます。
囲碁と将棋の基本的な違いと特徴
囲碁の特徴
囲碁は「黒」と「白」の石を使って陣地を取り合うゲームです。
ルールはシンプルですが、奥が深く、特に9路盤(小さな盤面)では短時間で相手の意図を読む判断力が求められます。
囲碁の思考は全体を俯瞰して構成する力=右脳を大きく使うと言われており、直感力・イメージ力を養うのに効果的です。
将棋の特徴
将棋は駒ごとに動き方が決まっており、それを覚えることから始まります。
序盤は覚えることが多いですが、慣れてくると「相手が次にどう動くか」を考えながら駒を進めていく戦略性が強くなっていきます。
将棋は論理的思考をフル活用する左脳を鍛えるのに最適です。
何手も先を読んで行動を選択する力は、算数・数学の応用力や読解力の向上にもつながります。
学習に役立つ3つのポイント
右脳と左脳をバランスよく使う
囲碁は「空間認識」や「全体を俯瞰する力」に優れており、将棋は「論理性」や「手順の構築力」を育ててくれます。
実際、プロ棋士の中には囲碁と将棋を両方たしなむ方も多く、片方で頭を疲れたらもう片方で気分転換をすることもあるそうです。
このように両方をバランスよく取り入れることで、より柔軟で強靭な思考力が育まれます。
「先を読む力」が身につく
囲碁や将棋では、「今この一手」が何手先にどう影響するかを考えることが重要です。
これは、試験問題における設問の意図を読み解いたり、複数の選択肢から最適解を選ぶ際の判断力と非常に似ています。
実際に囲碁や将棋が得意な生徒は、文章問題や数学の応用問題でも「思考の筋道」が自然と通るようになる傾向があります。
自分なりの解き方(戦法)を身につけられる
囲碁や将棋には「定石(定番の戦法)」が存在しますが、それに縛られる必要はありません。むしろ、どんどん自分なりの作戦を考え、試し、成功体験を積んでいくことができます。
これは学習においても同じ。
自分に合った「覚え方」「解き方」を見つける経験こそが、学習への自信と習慣化につながるのです。
「勉強が苦手な子」ほど囲碁・将棋を!
実は、学校や塾の授業で伸び悩んでいた生徒が、囲碁や将棋をきっかけに劇的に変わった例もあります。
- 難しいことにも挑戦する姿勢が身についた
- 間違いを恐れず「次の一手」を打てるようになった
- 時間内に答えを導く集中力と瞬発力が上がった
このような変化は、単に知識をインプットするだけでは得られません。
囲碁や将棋を通して「自分の頭で考える」ことの楽しさに目覚めることが、すべての学力向上の“種”になるのです。
塾の指導にも活かせる囲碁・将棋的アプローチ
櫻學舎では、単に教科書の知識を教えるのではなく、「考え方の筋道をつける」指導を重視しています。
たとえば…
- 文章題を「囲碁のように」全体を俯瞰して解く力
- 数式の変形を「将棋のように」一手ずつ整理して進める力
これらはまさに、囲碁・将棋の思考法がそのまま活きる場面です。
まとめ|囲碁・将棋は「学びの力」を育てるゲーム
スマホゲームや短期的な刺激も楽しいですが、囲碁や将棋のように「じっくり考えて結果を出す」体験は、今後ますます必要とされる力になります。
ぜひ、家庭での遊びや、勉強の息抜きとして、囲碁や将棋を取り入れてみてください。
そして、「遊びながら考える力が育つ」その感覚を、ぜひ子どもたち自身に感じてもらえたらと思います。
櫻學舎では、囲碁や将棋を通じた思考トレーニングにも柔軟に取り組んでいます。
ご興味ある方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。








