片手で31まで数える!?|2進法で広がる数字の世界と中学入試・数学の楽しさ
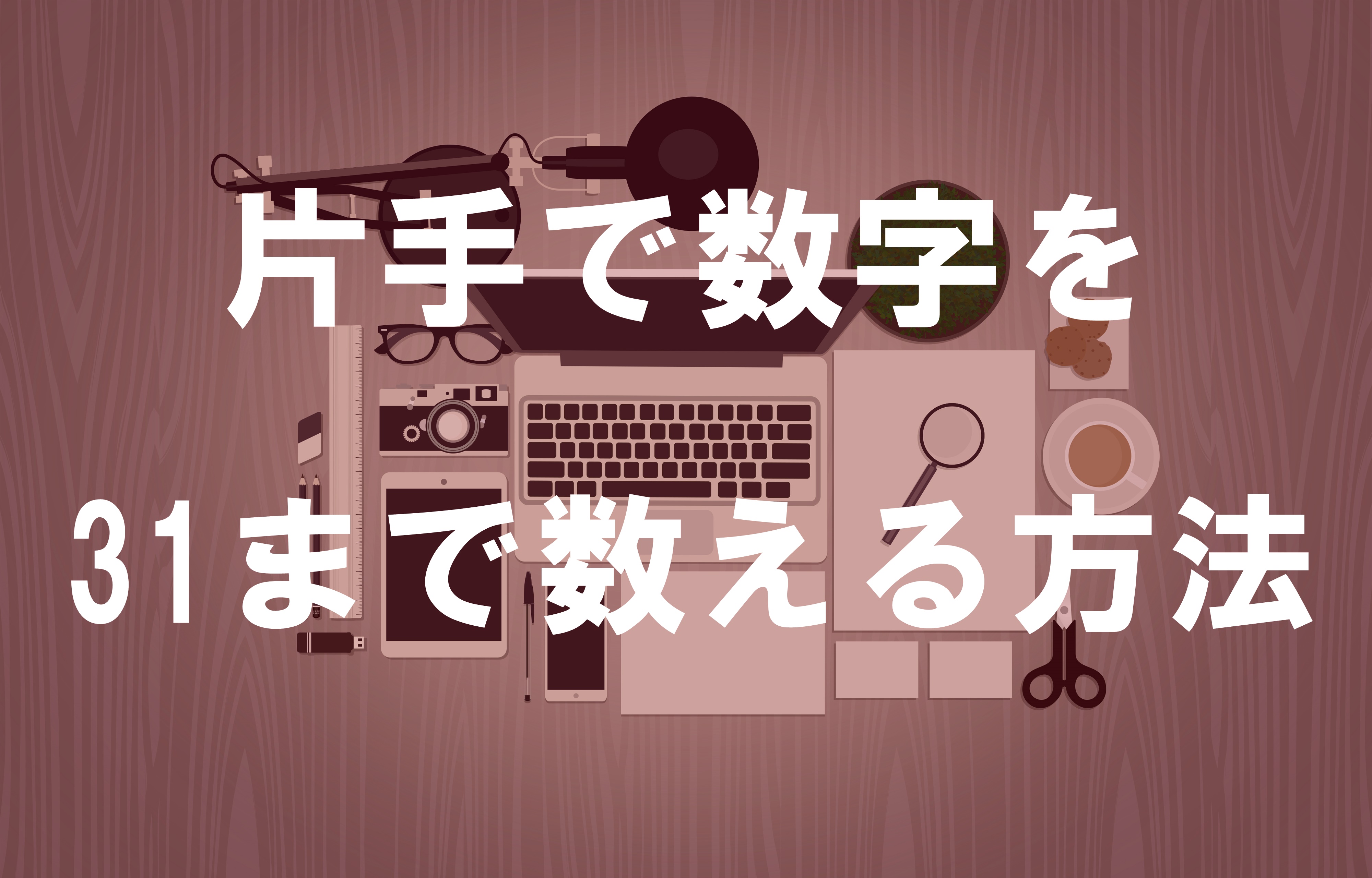
片手で、いくつまで数えられますか?
ジャンケンの「パー」から親指を1本ずつ折っていけば5まで。ちょっと工夫して10まで数えられる人もいるかもしれません。でも、もし「片手だけで31まで数えられる」と言われたら、驚く人がほとんどではないでしょうか?
そのカギは、「2進法(にしんほう)」にあります。
普段私たちが使っているのは0~9の数字を使う「10進法」ですが、実は世の中にはさまざまな“進法”があり、その代表格が「2進法」。これは、コンピューターの世界でも標準となっている数の数え方です。
この記事では、「なぜ片手で31まで数えられるのか?」「2進法とは何か?」を小学生でも楽しくわかるように解説しながら、数学の奥深さと面白さを伝えていきます。
ちょっと不思議で、でも実はとても実用的な「数字の世界」へ、一緒に足を踏み入れてみませんか?
片手で数を数えるふつうの方法
まずは、私たちが普段どのように「手」を使って数を数えているかを確認してみましょう。
多くの人が思い浮かべるのは、ジャンケンの「パー」の状態から、1本ずつ指を折っていく方法ではないでしょうか?
- 親指を折って「1」
- 人差し指も折って「2」
- 中指、薬指、小指…と順に折っていき、全部折ると「5」
この方法で数えられるのは、片手で1〜5まで。ここまでは多くの人が自然にできるはずです。
もう少し工夫できる人なら、指を1本ずつ立てていく逆パターンで、グー(全部折った状態)を「6」、小指だけ立てて「7」…というふうに数え、最大「10」まで数えるかもしれません。
けれども、ここで限界が来てしまいます。
なぜなら、指の本数は5本しかないため、同じ形が別の数字として重なってしまうからです。
たとえば、「1」は親指だけ折る形ですが、そこから「11」を数えようとすると同じ形になってしまい、区別ができません。
このように、通常の方法では片手で数えられるのはせいぜい10まで。
「31まで数える」なんてとても無理そうに思えますが、ここで登場するのが“2進法”という新しい数の考え方です。これを使えば、たった片手だけで0から31まで、32通りの数を表すことができるのです。
次のセクションでは、その秘密を解き明かしていきましょう。
実は片手で31まで数えられる!

「片手で31まで数えられるなんて本当?」
そう思った方もいるかもしれません。でも、それは2進法の考え方を使えば、可能なのです。
そもそも「2進法」とは?
私たちが普段使っている数字は「10進法」と呼ばれ、0~9の10種類の数字を使います。
1の位、10の位、100の位…というように、桁がひとつ上がるたびに10倍になります。
一方、2進法は「0と1の2つの数字だけ」を使う数の表現方法です。
桁が上がるごとに「2倍」になっていくのが特徴で、
- 1の位
- 2の位
- 4の位
- 8の位
- 16の位
というように、2・4・8・16…と増えていきます。
9を2進法で表すと?
たとえば、10進法の「9」は、2進法ではこう表されます。
1001
これはどういうことかというと、
- 1(8の位) × 1 = 8
- 0(4の位) × 0 = 0
- 0(2の位) × 0 = 0
- 1(1の位) × 1 = 1
→ 合計 8 + 1 = 9
となり、確かに「9」になります。
このように、指を2進法の桁に見立てれば、数字を手で表現することができるのです。
指で数を表す!「2進法の指使い」
そこで、次のようにそれぞれの指を2進法の桁に対応させます。
- 親指 = 1の位
- 人差し指 = 2の位
- 中指 = 4の位
- 薬指 = 8の位
- 小指 = 16の位
そして、
- 指を折る=1(オン)
- 指を開く=0(オフ)
とルールを決めます。
このルールに従えば、指の折り方を変えることで、0〜31の32通りの数字を表せるようになるのです!
たとえば、
- 親指だけ折る → 1
- 人差し指と薬指を折る → 2 + 8 = 10
- 親指・中指・薬指を折る → 1 + 4 + 8 = 13
- 小指と薬指を折る → 16 + 8 = 24
- すべての指を折る → 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31
となります。
このように、たった5本の指でも、2進法を使えば31まで表現できるのです。
遊び感覚で楽しみながら、自然と数学の本質にも触れられる…
それが「2進法の指遊び」のおもしろさです。次は、実際にクイズで試してみましょう!
実践!クイズで2進法を理解しよう
2進法のルールと指の対応がわかったところで、ここからは実際にクイズ形式で2進法の感覚をつかんでみましょう。
指のルールはこうでしたね。
- 指を折る →「1」=その位の値を加算
- 指を開く →「0」=加算しない
指の対応は以下のとおりです。
- 親指 = 1の位
- 人差し指 = 2の位
- 中指 = 4の位
- 薬指 = 8の位
- 小指 = 16の位
それではクイズにチャレンジしてみましょう!
Q1. 親指だけを折った状態の数字は?
答え:1
Q2. 薬指と人差し指を折り、他は開いている場合は?
答え:10
Q3. 「13」を表すには、どの指を折ればいい?
答え:親指・中指・薬指
Q4. 「24」を表すには?
答え:小指と薬指
Q5. すべての指を折ると何になる?
答え:31
このように、指の組み合わせだけで0から31までのすべての数を表現できるのが、2進法のすごいところです。
最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてくると自分の手がまるで「ビットマシン」のように見えてきます。
算数や数学に苦手意識がある人でも、「遊び」として楽しめるのが、この2進法クイズの魅力です。
ぜひ、お子さんやご家族と一緒に試してみてください!
数学がもっと身近で楽しいものに感じられるはずです。
コンピューターも使っている2進法の世界

ここまでで、「2進法って意外とおもしろい!」と感じていただけたのではないでしょうか?
実はこの2進法、ただの指遊びや数学のおもしろネタではありません。
現代社会のあらゆる場面で活躍している、超重要な数の表現方法なのです。
コンピューターは0と1で動いている
私たちが日々使っているスマートフォンやパソコン、ゲーム機やテレビなど、あらゆる電子機器の中で使われているのが、この「2進法」です。
なぜなら、コンピューターの中ではすべての情報を「電気が流れている(1)」または「流れていない(0)」という2つの状態だけで表現する必要があるからです。
例えば、
- 画像 → 色や明るさの情報も0と1に変換されて処理
- 音楽 → 音の高さや長さも0と1の組み合わせで表現
- 文字 → 「A」「B」「あ」「い」も、全部2進数に変換して認識される
つまり、この世界のあらゆる“デジタルなもの”は、2進法によって成り立っているということなのです。
身近にある「N進法」
実は私たちの生活の中には、10進法や2進法だけでなく、さまざまな進法(N進法)が自然に使われている場面があります。
- 時計 → 12時間で1周=「12進法」
- 1分=60秒、1時間=60分 → 「60進法」
- 日常的な「午前・午後」は12進法の名残とも言えます
このように、進法は身近な生活の中にもたくさん使われています。
だからこそ、2進法を知ることは、「算数・数学の勉強」だけにとどまらず、コンピューターリテラシーや論理的思考を育てる第一歩になるのです。
指で数を数える、というシンプルな遊びの中に、数学・テクノロジー・論理の世界の入口が隠れている。
2進法の知識は、まさに“未来のリテラシー”として、これからますます重要になっていくでしょう。
教育の視点:中学入試で学ぶN進法
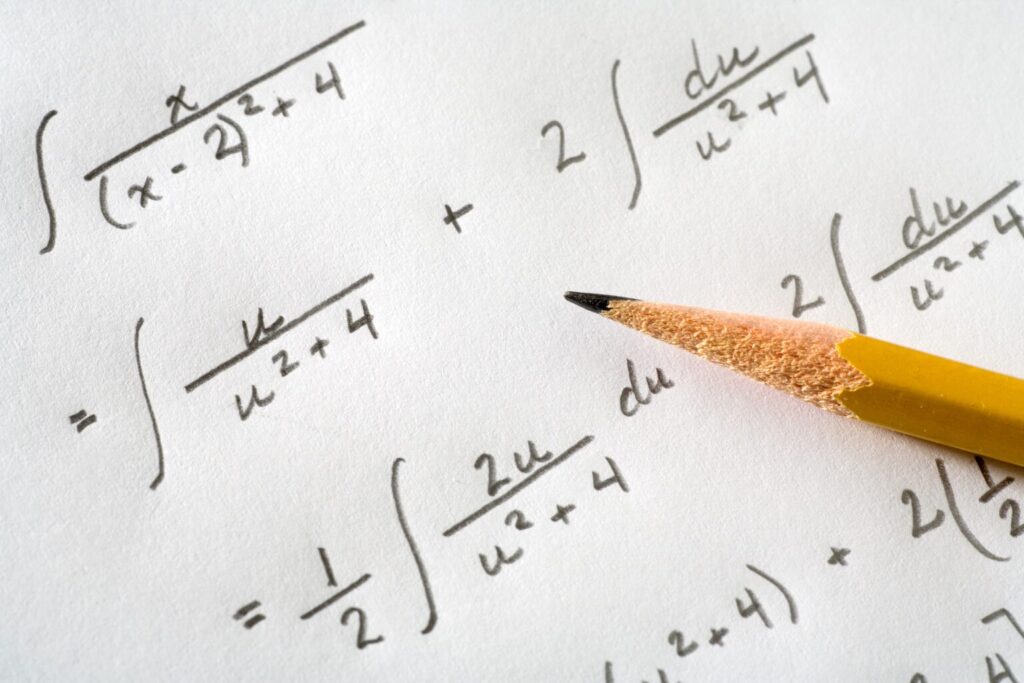
2進法やその他の「N進法(エヌしんほう)」は、実は中学受験において出題されることのある重要単元の一つです。
中学入試では、「数の仕組みを深く理解しているか」「論理的に考えられるか」を見る問題が出題されるため、10進法とは異なる数の表し方であるN進法がよく使われるのです。
N進法とは何か?
「N進法」とは、1つの桁に使う数字の種類がN個ある数の表現方法のこと。
普段の「10進法」は、0〜9の10種類を使うので「N=10」の進法です。
一方で、
- 2進法(N=2)…0と1だけを使う
- 3進法(N=3)…0, 1, 2 を使う
- 8進法、12進法、16進法なども存在します
これらの考え方は、「数とは何か?」「位取りとは何か?」という算数の本質を理解するうえで非常に有効です。
どんな問題が出るの?
中学入試では、以下のような問題が見られます。
- 「2進法で表された数を10進法に直す」
- 「N進法で数を数える規則性を見つける」
- 「特定のN進法で〇番目の数を求める」
たとえば、片手の指の折り方を使って「2進法で数を数える」ような遊びは、そのまま規則性・数の構造・思考力を問う問題のトレーニングにもなります。
中学生・高校生では扱われない?
N進法は小学校の教科書にはほとんど載っておらず、中学受験をする小学生向けの特別な単元とされることが多いです。
そのため、中学生や高校生であっても触れる機会が少なく、知っていると差がつく知識のひとつとも言えます。
算数や数学が「苦手」と感じるお子さんでも、2進法を使って指で遊びながら学べば、自然と論理的な思考力が身につく可能性もあります。
遊びと学びをつなぐ「N進法」。
学びの入り口として、家庭での会話やちょっとしたチャレンジに取り入れてみてはいかがでしょうか?
まとめ:数字の世界を広げよう

普段、私たちは「10進法」という決まったルールの中で数字を扱っています。
でも、今回ご紹介した「2進法」のように、数字の世界にはまだまだたくさんの“ルール”や“見方”があることに気づけたのではないでしょうか。
ジャンケンの「パー」や「グー」で終わっていた指の使い方も、考え方を少し変えるだけで、片手で31まで数えられる高度な数学的表現に早変わりします。
このように、ちょっとしたきっかけで「当たり前」が変わる体験は、子どもたちにとっても大人にとっても、とても刺激的で学びのある時間です。
また、2進法はコンピューターの仕組みを理解する第一歩でもあり、情報社会を生きる上で欠かせない「数字と論理のリテラシー」を育むチャンスでもあります。
さらに、N進法は中学受験でも出題される単元でありながら、中高ではあまり触れられない分野。
知っているだけで差がつく、ちょっと得する知識としても役立ちます。
ぜひ、ご家庭でも「2進法って知ってる?」と話題にしてみてください。
楽しく遊びながら、いつの間にか“数学の世界”に一歩踏み込める。
そんなきっかけになれば嬉しいです。
数字の世界は、思っているよりもずっと自由でおもしろいもの。
これからも、学びの幅をどんどん広げていきましょう!








