作文と小論文の違いを徹底解説!入試で失敗しないための基礎と考え方
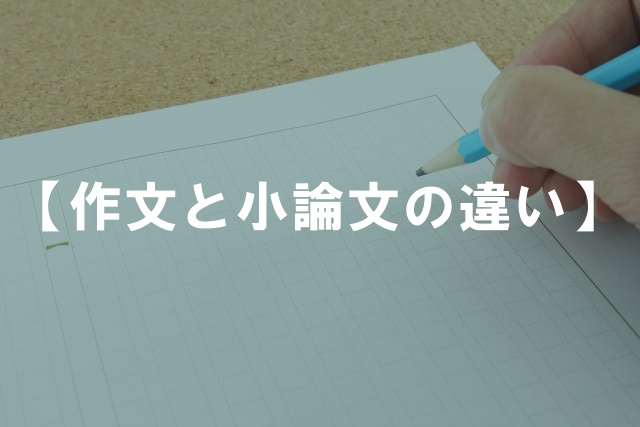
「先生、小論文って作文と何が違うんですか?」
毎年、入試シーズンになると必ず出てくるこの質問。
高校入試や大学入試の推薦・総合型選抜では、小論文が出題されることも珍しくありません。しかし、作文と小論文の違いを理解しないまま書き始めると、せっかくの文章が減点対象になったり、的外れな内容になってしまうこともあります。
小論文は「感情を伝える文章」ではなく、「意見と根拠で相手を説得する文章」です。
この記事では、作文と小論文の明確な違いを例文付きでわかりやすく解説し、入試で評価される小論文を書くための基礎をお伝えします。
小論文とは何か?作文との違い
同じ「文章を書く」でも、作文と小論文は目的も内容もまったく違います。
違いを知らないまま書くと、入試で「テーマから外れている」と判断され、評価が下がってしまうこともあります。
作文とは
- 自分の体験や感情を中心に書く文章
- 読み手の「心」に響かせることが目的
- 例:「修学旅行で楽しかった思い出」「部活で頑張ったエピソード」
小論文とは
- 自分の意見と、その根拠を論理的に書く文章
- 読み手の「頭」を納得させることが目的
- 例:「修学旅行が学校教育に必要な理由」「部活動が地域社会に与える影響」
大きな違いは「感情」か「意見+根拠」か
作文は感情や経験をありのままに書きますが、小論文では感情を排して、主張と理由を筋道立てて書きます。
言い換えると──
- 作文=思ったことや感じたことを書く
- 小論文=考えたことを理由とともに説明する
覚えておきたいポイント
作文という大きなジャンルの中に、小論文という種類があるイメージを持ちましょう。
ただし、入試で出される小論文は、作文よりもはるかに論理性・説得力・一貫性が求められます。
感情表現だけでまとめてしまうと、「作文」とみなされ、評価が低くなる可能性があります。
例文で理解する「どちらが小論文か?」
作文と小論文の違いは、「感情や体験を中心に書くか」「意見と根拠を中心に書くか」です。
ですが、この違いは頭でわかっていても、実際の文章を見ると迷ってしまうことがあります。そこで、具体例を使って確認してみましょう。
テーマ:「動物園について」
文章A:動物園に行きました。たくさんの動物を見ることができて、とても楽しかったです。
文章B:動物園は、多くの貴重な動物を保護するという役割を果たしている。
どちらが小論文か?
正解は 文章B です。
文章Aの特徴(作文)
- 「楽しかった」という感想が中心
- 動物園に行った体験と、その時の感情を述べている
- 事実や意見は少なく、読み手の「心」に訴える形になっている
- もし続きを書くとすれば、「どんな動物を見たか」「どんな気持ちになったか」が中心になる
このような文章は、作文としては評価されますが、小論文の評価基準で見ると「意見がない」「根拠がない」と判断されます。
文章Bの特徴(小論文)
- 「動物園は動物を保護する役割がある」という主張(意見)を明確にしている
- 読み手の「頭」を納得させるための書き出しになっている
- もし続きを書くとすれば、「なぜそう言えるのか?」という根拠や「具体例」「データ」などを加えて論理的に展開できる
- 感情表現はなく、客観的な視点が中心
このように、小論文はまず主張を提示し、根拠で支えるという構造を持ちます。
見分け方のコツ
- 感情・体験中心 → 作文
- 意見・根拠中心 → 小論文
小論文では、感情表現や体験談を使う場合もありますが、それは主張を補強する目的で使います。感情そのものが文章の中心になってはいけません。
この「感情と意見の違い」を意識できるようになると、書き始めの一文で自分が作文を書いているのか小論文を書いているのかがすぐにわかるようになります。
小論文を書くときの基本ルール
小論文は「意見と根拠で相手を説得する文章」です。
そのためには、書き始める前から構造・視点・表現の3つを意識することが大切です。ここでは、入試で評価されるための基本ルールを整理します。
① 主張(意見)をはっきり示す
小論文は「自分はこう考える」という立場を明確にすることから始まります。あいまいな書き出しや、結論が最後までぼやけている文章は減点対象になりやすいです。
例:✕「動物園には色々な役割があります。」
〇「動物園は、絶滅の危機にある動物を保護する上で重要な役割を果たしている。」
② 根拠を必ず添える
意見だけでは「ただの感想」で終わってしまいます。「なぜそう思うのか?」という理由を必ず書きましょう。根拠は、データ、事実、事例、経験など、できるだけ具体的なものが望ましいです。
例:「保護活動の成果として、パンダの個体数が回復している事例がある。」
③ 序論→本論→結論の構成を守る
読み手にわかりやすく伝えるためには、文章の順序を整えることが大切です。
- 序論:テーマ提示+自分の意見
- 本論:意見の根拠・具体例・反対意見への対応
- 結論:意見の再提示+まとめ
この型を使うと、論理の流れが自然になり、読み手に伝わりやすくなります。
④ 感情表現を控え、客観性を保つ
小論文は「頭で納得させる文章」です。「楽しい」「最高!」などの感情表現は避け、客観的な言い方に変えます。
例:✕「動物園はかわいい動物がいて最高です!」
〇「動物園は教育・研究・保護の場として社会的な価値が高い。」
⑤ 一貫性を保つ
文章全体を通して、意見や立場がぶれないようにしましょう。序論で述べた主張と結論が一致していることが重要です。本論の根拠や事例も、最初の意見を支える内容に限定します。
この5つのルールを意識すれば、文章の形が自然と整い、読み手に伝わる小論文になります。あとは日々の練習で、主張や根拠をスムーズに書けるようにしていきましょう。
入試で求められる小論文力
入試の小論文は、単に文章を書けるかどうかではなく、与えられたテーマについて自分の意見を筋道立てて表現できるかを試す課題です。評価されるのは“文章力”だけではなく、“考える力”や“伝える力”も含まれます。
① 論理性(話の筋が通っているか)
自分の意見と理由がきちんとつながっていることが大切です。「なぜそう考えるのか?」が明確で、話の順序が自然であると、読み手は迷わず内容を理解できます。意見と根拠がバラバラだと、どんなに文章が上手でも説得力は下がってしまいます。
② 一貫性(意見がぶれない)
序論で述べた意見を、結論まで変えずに貫くことが必要です。途中で話題が変わったり、別の立場をとってしまうと、全体のまとまりがなくなります。本論で使う根拠や事例は、必ず最初の主張を支える内容にしましょう。
③ 説得力(理由が具体的か)
「面白いから」「大事だと思うから」などの抽象的な理由だけでは説得力が足りません。数字や事実、具体的な事例を示すことで、意見が現実的で信頼できるものになります。また、反対意見に少し触れた上で「それでも自分はこう考える」と書くと、より強い文章になります。
④ 表現力(読みやすさ)
正しい日本語を使い、主語と述語の関係がねじれないように注意します。漢字の間違いや不自然な言い回しは減点対象になります。短くはっきりした文で書くことを意識すると、読み手に負担をかけず、内容がスムーズに伝わります。
⑤ 問題理解力(テーマに沿っているか)
出題されたテーマや資料の内容を正しく理解し、それに沿った文章を書くことが基本です。テーマから外れた内容や、自分の関心だけを書き連ねた文章は評価されません。問題文や資料を丁寧に読み取り、設問に合った答え方をすることが求められます。
これら5つの力は、どれか一つ欠けても評価が下がる可能性があります。小論文は、考える力、文章を組み立てる力、そして正確に表現する力をバランスよく発揮してこそ、読み手を納得させられる文章になります。
保護者・先生ができるサポート例
小論文は一人で練習することも大切ですが、保護者や先生など身近な大人の関わりがあると、上達のスピードが大きく変わります。とくに「考えを整理して伝える力」は、日常的な会話ややり取りの中で育てられます。
まず効果的なのは、子どもが何か意見を口にしたときに「どうしてそう思うの?」と理由を尋ねることです。理由を言葉にする習慣は、小論文に欠かせない“根拠を示す力”のトレーニングになります。また、ニュースや新聞記事を一緒に見ながら「賛成?反対?」「その理由は?」と意見を交換するのも有効です。異なる意見に触れることで、自分の考えを整理する練習にもなります。
さらに、感情表現と意見の違いを意識させることも重要です。たとえば「楽しい」「面白い」といった感想と、「必要だ」「効果がある」といった意見を区別できるように指導します。実際の文章で感情部分に印をつけ、意見として書き換える練習を一緒に行うと、文章の客観性が高まります。
書く前の準備としては、「序論・本論・結論」の構成メモを一緒に作るのがおすすめです。書き終えたあとにメモと文章を比べ、話がぶれていないかを確認すると構成力が伸びます。また、短時間で「意見+理由」を説明する練習も効果的です。1分以内でまとめて話すことで、文章にしても無駄が少なく、説得力のある内容になっていきます。
このように、保護者や先生が日常の中で問いかけや意見交換の機会をつくることは、単なる文章指導以上の効果があります。小論文の力は、机の上だけではなく、普段の会話や思考の習慣からも養われるのです。
まとめ
作文と小論文は、同じ「文章を書く」という行為でも、目的も書き方もまったく違います。
作文は感情や体験を中心に「心に響かせる」文章、小論文は意見と根拠を筋道立てて「頭を納得させる」文章です。この違いを理解しないまま書くと、せっかくの努力が入試で正しく評価されないこともあります。
小論文で大切なのは、はっきりとした主張を持ち、その理由を具体的な事実や事例で支えること。そして、序論→本論→結論の順序で文章を組み立て、最後まで一貫性を保つことです。こうした書き方は一朝一夕では身につきませんが、日常生活の中で「なぜ?」と考え、意見を言葉にする習慣を持てば、少しずつ力がついていきます。
入試の小論文は、「考える力」「組み立てる力」「表現する力」の総合テストです。
日々の会話や練習を通じてこれらを磨き、自信を持って自分の意見を伝えられる文章を書けるようにしていきましょう。








